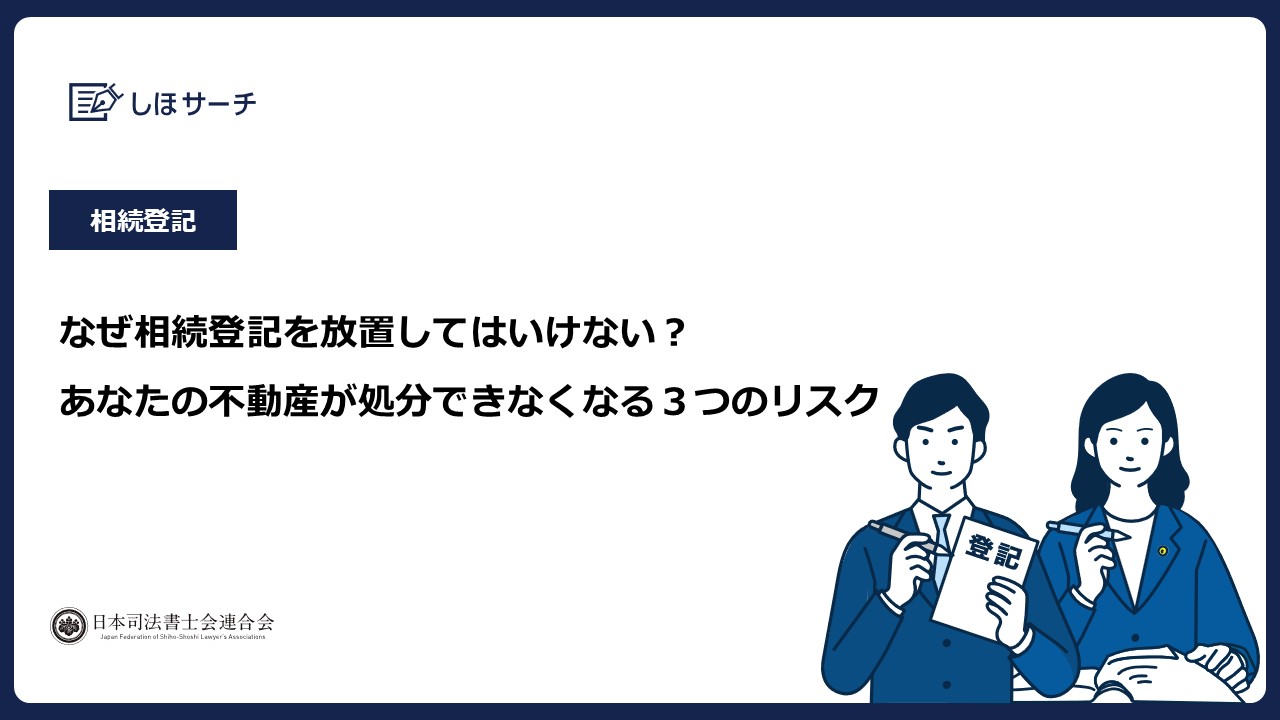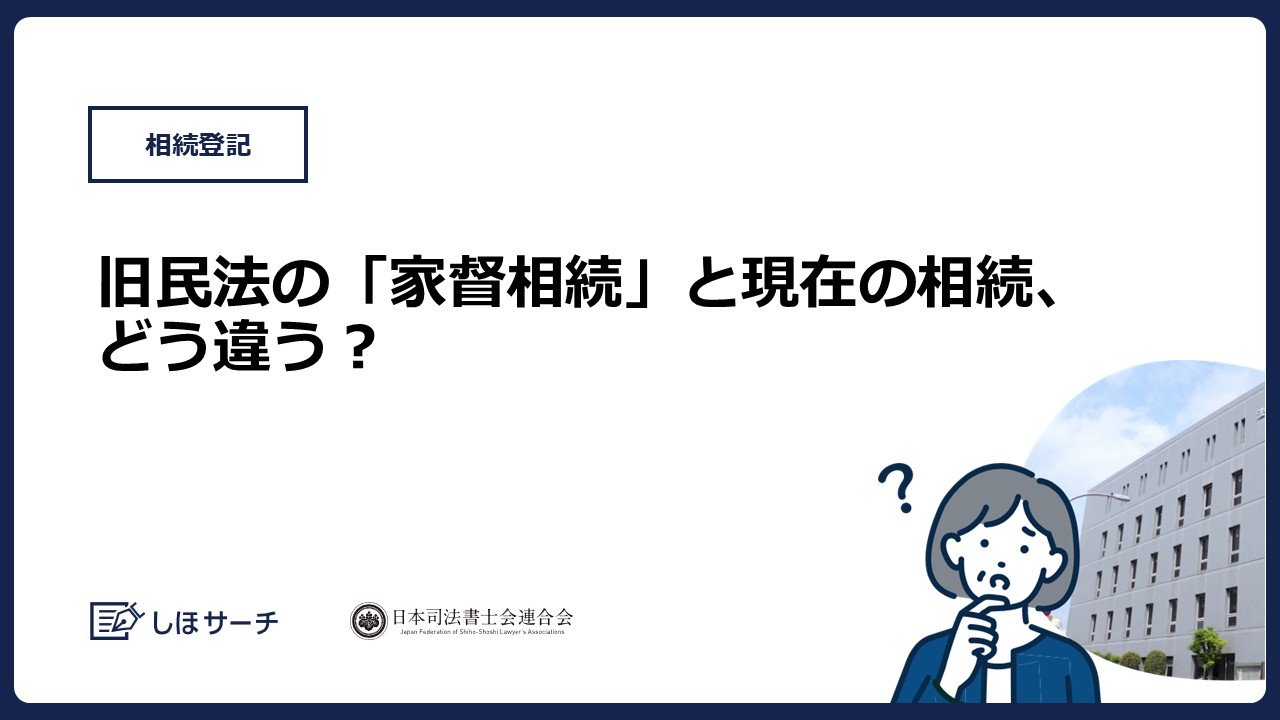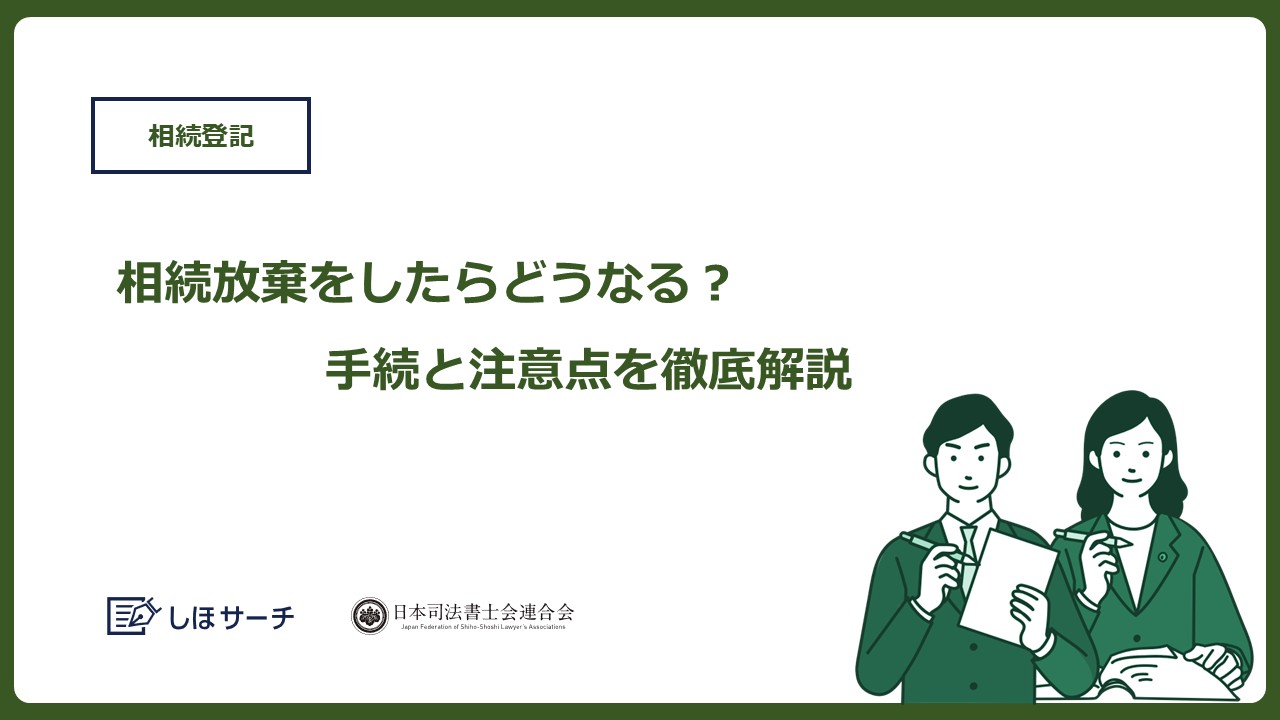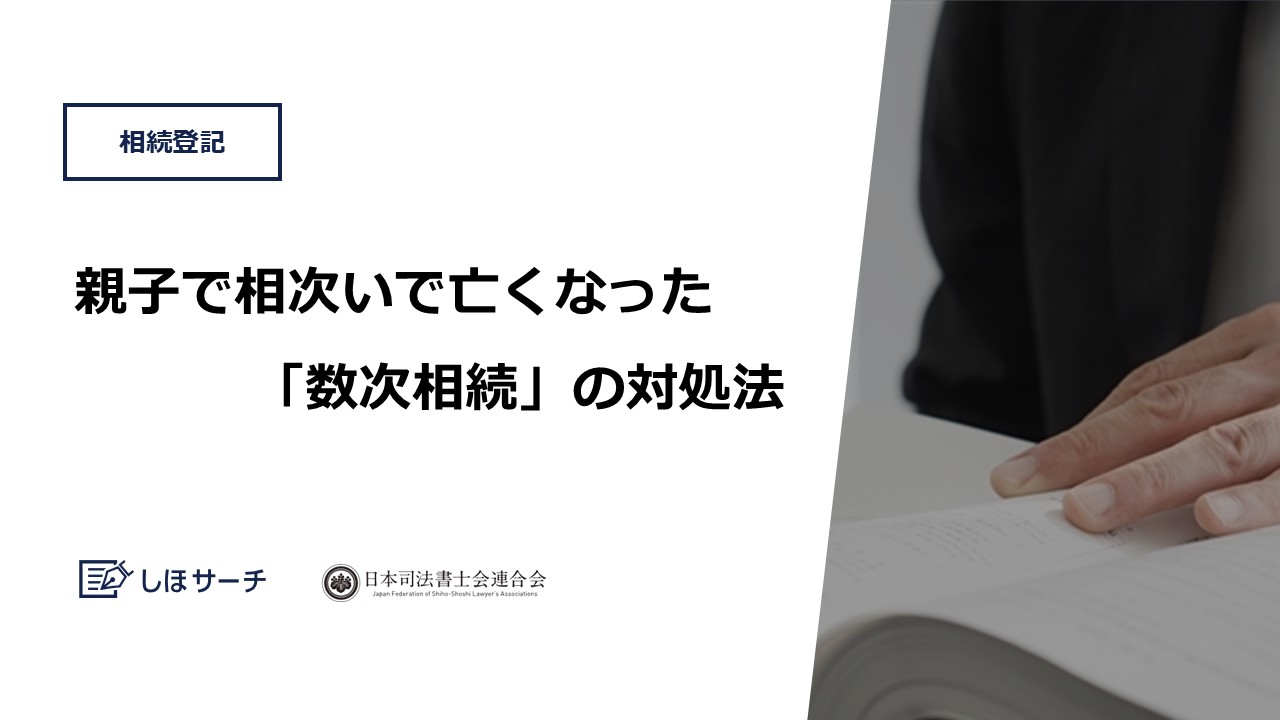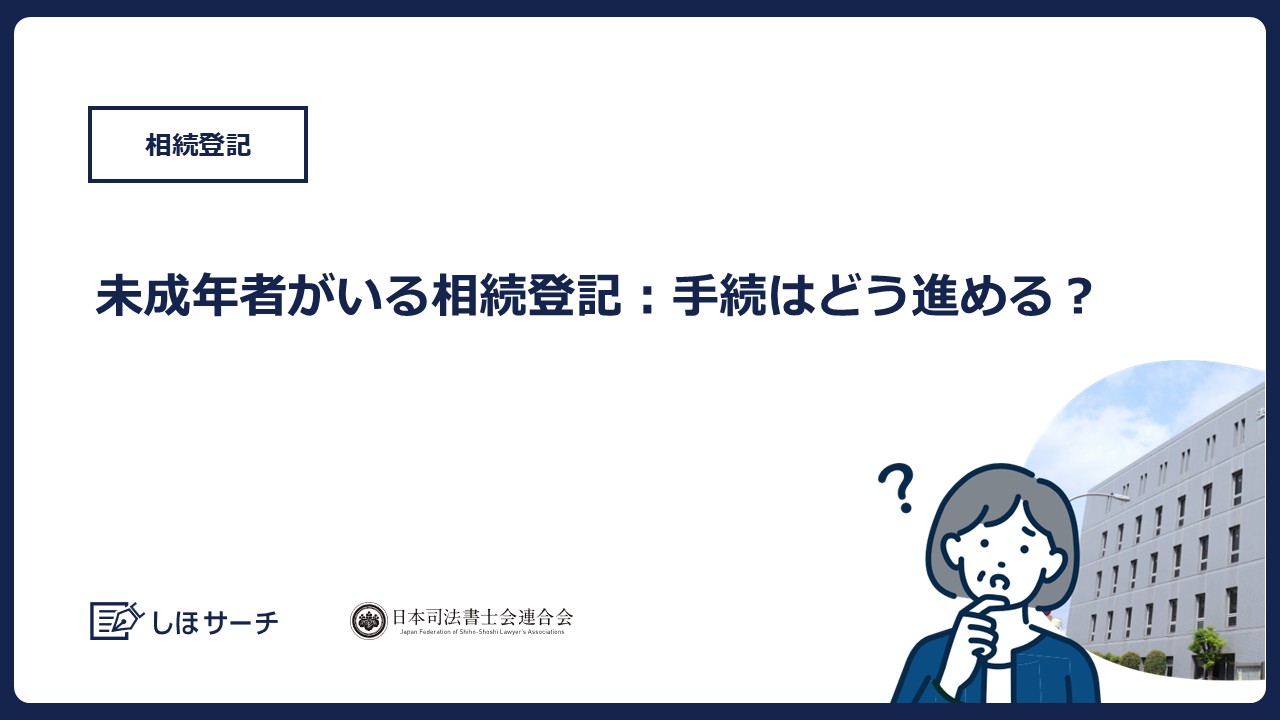なぜ相続登記を放置してはいけない?あなたの不動産が処分できなくなる3つのリスク
はじめに
親が亡くなって実家を相続したものの、「登記の手続は面倒だし、今すぐ売るわけでもないから、相続登記は後でいいか」と考えていませんか?実は、相続登記を放置することは、将来あなたやご家族に大きな問題を引き起こす可能性があります。
令和6年4月から相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。しかし、それ以上に深刻なのは、相続登記の申請を放置することで不動産が事実上「処分できない財産」になってしまうリスクが発生することです。
この記事では、相続登記の申請を放置することで起こり得る3つの重大なリスクについて、具体的な事例を交えながらわかりやすく解説します。
リスク1:相続人が増え続け、話がまとまらなくなる
(1)時間が経つほど相続人は増えていく
相続登記の申請を放置する最も大きなリスクは、時間が経過するにつれて相続人が次々と増えてしまうことです。
例えば、あなたのお父様が亡くなって、相続人がお母様とあなた、そして弟の3人だったとします。この段階で話し合い、誰が不動産を相続するかを決めておけば、相続登記を申請することができます。
しかし、相続登記をしないまま10年、20年と時間が経過したらどうなるでしょうか?
たとえば弟に子どもが生まれ、その後、話し合いをする前にその弟が亡くなると、弟の配偶者や子どもたちがお父様の相続に係る相続人になります。このように、時間が経てば経つほど、相続人は増えていくことになります。そのほか、相続人の中に未成年者や判断能力が衰えてきた方が存在する可能性も生じることから、手続が複雑になっていきます。
(2)なぜ話がまとまらなくなるのか
相続人が増えると、以下のような問題が生じます。
・意見の対立が起きやすい
相続人が3人なら「売却して現金で分けよう」という話もスムーズにまとまるかもしれません。しかし、相続人が10人、20人となると、「売りたい人」「住み続けたい人」「とりあえず持っていたい人」など、様々な考えを持つ人が出てきます。全員の利害を調整することは極めて困難です。
・面識のない相続人との交渉
世代が離れ、一度も会ったことがない相続人同士では、信頼関係を築くことも難しく、交渉が長期化しやすくなります。
・一人でも反対者がいれば進まない
遺産分割は、原則として全員の同意が必要です。相続人が30人いたとして、29人が遺産分割協議案に賛成しても1人が反対すれば話は進みません。放置すればするほど、この「話がまとまらない」リスクは確実に高まっていくのです。
リスク2:第三者が権利を取得して割り込んでくる可能性
(1)法定相続分での登記という落とし穴
相続登記の申請を放置していると、相続人の一人が単独行為により「法定相続分」で登記を申請することがあります。これは、法律上は可能な手続です。
法定相続分とは、法律で定められた相続分の割合のことです。例えば、配偶者と子ども2人が相続人なら、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつとなります。
この法定相続分に基づく登記は、他の相続人が関与しなくても、単独で申請することができます。
(2)何が問題なのか
「相続人の一人が登記を入れてくれるなら、むしろ助かるのでは?」と思われるかもしれません。しかし、ここに大きな落とし穴があります。
考えられる問題として、各相続人は自分の持分(権利の割合)を、他の相続人の同意なく第三者に売却できてしまうということがあります。以下、シナリオに沿って確認します。
(3)具体的なリスクシナリオ
あなたの家族が相続した実家のケースで考えてみましょう。
1.相続人は、あなた、弟、妹の3人
2.弟が経済的に困窮し、借金を抱えている
3.弟が単独で法定相続分(3分の1)で相続登記の申請
4.弟が自分の持分(3分の1)を、借金返済のために不動産業者に売却
5.見知らぬ不動産業者が、実家の3分の1の権利を持つ共有者になる
こうなってしまうと、実家を売却しようにも、その不動産業者の同意が必要になります。業者は当然、「買い取り価格を上げてほしい」などの条件を出してくるでしょう。他の相続人に対し、低額の金額で持分の買取請求や、共有物分割請求訴訟への対応が迫られる可能性もあります。
(4)さらに深刻なケース:債権者による差押え
さらに深刻なのは、相続人の一人に多額の借金がある場合です。
法定相続分で登記がされると、その相続人の債権者(お金を貸している人)は、その持分を差し押さえることができます。差し押さえられた持分は、競売手続の中で、第三者に売却されてしまう可能性があります。
このような事態を防ぐためには、相続が発生したら速やかに相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がその不動産を相続するのかを決めて、その内容で相続登記の申請をすることが重要です。
(5)予防策:遺産分割協議を適切に行う
意図しない法定相続分での登記を防止するためには、相続発生後速やかに相続人全員で話し合い、遺産分割協議を行うことが大切です。
遺産分割協議が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、全員が署名・押印します。この遺産分割協議書に基づいて単独所有とする相続登記をすれば、特定の相続人が単独で不動産を所有することになり、第三者が割り込んでくるリスクを回避できます。
リスク3:相続人が認知症になると手続が極めて困難に
(1)高齢化社会で増える「判断能力」の問題
相続登記を放置する第3のリスクは、時間が経過する中で相続人の誰かが認知症などにより判断能力を失ってしまうケースです。
高齢化が進む現代社会において、このリスクは決して他人事ではありません。厚生労働省の推計によれば、65歳以上の高齢者の約3割が認知症又は軽度認知障害を有するとされています。
相続登記を「そのうちやればいい」と先延ばしにしている間に、相続人の一人が認知症を発症してしまう―このような状況は、想像以上に多いものと思われます。
(2)なぜ認知症の相続人がいると相続登記の申請が困難になるのか
相続登記の申請を行うには、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で不動産を相続するかを決める必要があります。この遺産分割協議を行うためには、遺産分割協議を行うことができる能力が必要とされています。
認知症などで判断能力が低下している方は、遺産分割協議を行うことができる能力を有しているか疑義が生じ得ることがあり、事案によっては、成年後見制度を利用する必要があります。
なぜなら、遺産分割は重要な財産の処分を伴う法律行為であり、その内容を理解し、自分の意思で判断する能力が求められるためです。
(3)ある事例から:母の認知症で進まなくなった相続登記
父親が亡くなり、相続人は母親、長男、次男の3人でした。父親名義の自宅不動産がありましたが、「母も住んでいるし、急ぐ必要もない」ということで、相続登記の申請を先延ばしにしていました。
それから5年後、長男が自宅を建て替えるために父親名義の土地を売却しようとしたところ、問題が発覚しました。母親が認知症を発症し、会話もほとんどできない状態になっていたのです。
医師の診断では、すでに遺産分割協議ができる判断能力はないとのことでした。
このままでは遺産分割協議ができないため、家庭裁判所に「成年後見人」を選任してもらう手続が必要になりました。結局、相続登記が完了するまでに、さらに1年以上の時間と別途の費用がかかることになってしまったのです。
(4)成年後見制度で手続を進めることはできるが……
認知症などで判断能力が衰えた相続人がいる場合、成年後見制度の活用を検討する必要があります。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わって、財産管理や身上保護などを行う人のことです。成年後見人が選任された場合、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
・申立てに時間と手間がかかる
成年後見人の選任を申し立てるには、医師の診断書、本人の財産目録、戸籍謄本など、多くの書類を準備する必要があります。申立てから審判が出るまで、一定の期間がかかります。
・本人に不利な遺産分割はできない
成年後見人は本人の利益を守る立場にあるため、本人に不利な内容の遺産分割協議は、原則として成立させません。例えば「母の取り分はゼロで、子どもたちだけで分ける」といった遺産分割協議案は、原則として認められず、法定相続分(この場合は母の法定相続分である2分の1)を確保する必要があります。
利益相反の問題:さらに複雑になるケース
もし母親が認知症で、その成年後見人に長男がなっていたとします。この状態で父親の遺産分割協議をする場合、さらに複雑になります。
長男は、自分自身の相続人としての立場と、母親の成年後見人としての立場になります。これは「利益相反」と呼ばれる状態で、長男が自分に有利な内容で遺産分割協議をまとめてしまうおそれがあるため、このままでは遺産分割協議を行うことができません。
この場合、家庭裁判所に「特別代理人」という、一時的に母親を代理する別の人を選任してもらう必要があります。特別代理人の選任手続についても時間や費用がかかります。
もっと深刻なケース:複数の相続人が認知症に
相続登記を10年、20年と放置していると、さらに深刻な事態も起こりえます。
例えば、当初の相続人が母親と子ども3人だったとして、その後母親が亡くなったとすると、次は子どもたちが相続人になります。しかし、その子どもたちのうち複数人が判断能力に衰えが生じていた場合、どうなるでしょうか。
先ほどの事例のように、それぞれ成年後見制度を利用する必要があり、手続の複雑さと費用は大きいものになります。
認知症は誰にでも起こりうる
「うちの家族はまだ若いから大丈夫」と思われるかもしれません。しかし、認知症は高齢者だけの問題ではありません。
若年性認知症は、65歳未満で発症する認知症で、働き盛りの40代、50代でも発症することがあります。また、脳血管疾患や事故による脳損傷などで、突然判断能力を失うこともあります。
相続登記を先延ばしにすればするほど、相続人の誰かが判断能力を失うリスクは高まっていきます。「今はみんな元気だから」という理由で相続登記の申請を放置することは、将来のリスクを大きくすることになるのです。
予防策:元気なうちに早めの手続きを
認知症のリスクを考えると、相続が発生したらできるだけ早く、相続人全員の判断能力があるうちに遺産分割協議を行い、相続登記を済ませることが何より重要です。
「面倒だから」「費用がかかるから」と先延ばしにした結果、成年後見制度の利用が必要になれば、さらに多くの時間と費用がかかることになります。
判断能力があるうちに、相続人の間でしっかり話し合い、相続登記を完了させておくこと―これが、将来の負担を大きく減らすことにつながるのです。
まとめ:今すぐ相続登記を済ませるべき理由
相続登記の申請を放置することで生じる3つのリスクについて解説してきました。
1.相続人が増え続けて話がまとまらなくなる
時間が経つほど相続人は増え、全員の同意を得ることが困難になります。
2.第三者が権利を取得する可能性
意図しない法定相続分での登記がされると、相続人の債権者や、持分を買い取った第三者が共有者になるリスクがあります。
3.認知症の相続人がいると手続が極めて困難に
成年後見制度の利用など、別途の手続が必要となり、時間や費用を要することとなります。
これらのリスクは、相続が発生したらできるだけ早く相続登記を行うことで、回避することができます。
相続登記は「いつかやればいい」手続きではありません。
令和6年4月からは相続登記の申請が法律上の義務となり、相続の開始を知り、所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、過料の対象となる可能性があります。しかし、それ以上に重要なのは、放置することであなたの大切な財産が「処分できない不動産」になってしまうということです。
「面倒だから」「費用がかかるから」と先延ばしにすればするほど、将来的に多くの手続と費用がかかる可能性があります。
もしあなたが相続した不動産で、まだ相続登記の申請をしていないものがあるなら、ぜひ今すぐ司法書士などの専門家に相談してください。早めの対応が、あなたとご家族の大切な財産を守ることにつながります。
相続登記でお困りのことがあれば、お近くの司法書士にお気軽にご相談ください。司法書士は、相続登記の専門家として、皆様の大切な財産をお守りするお手伝いをさせていただきます。