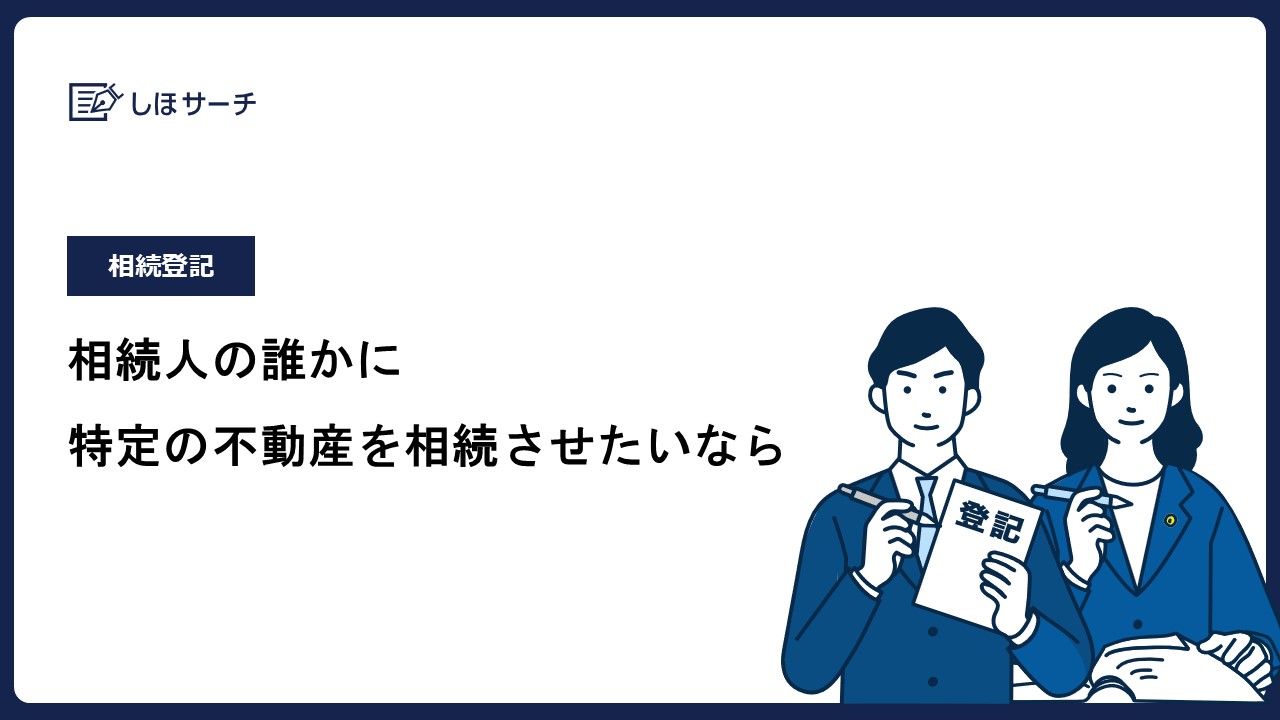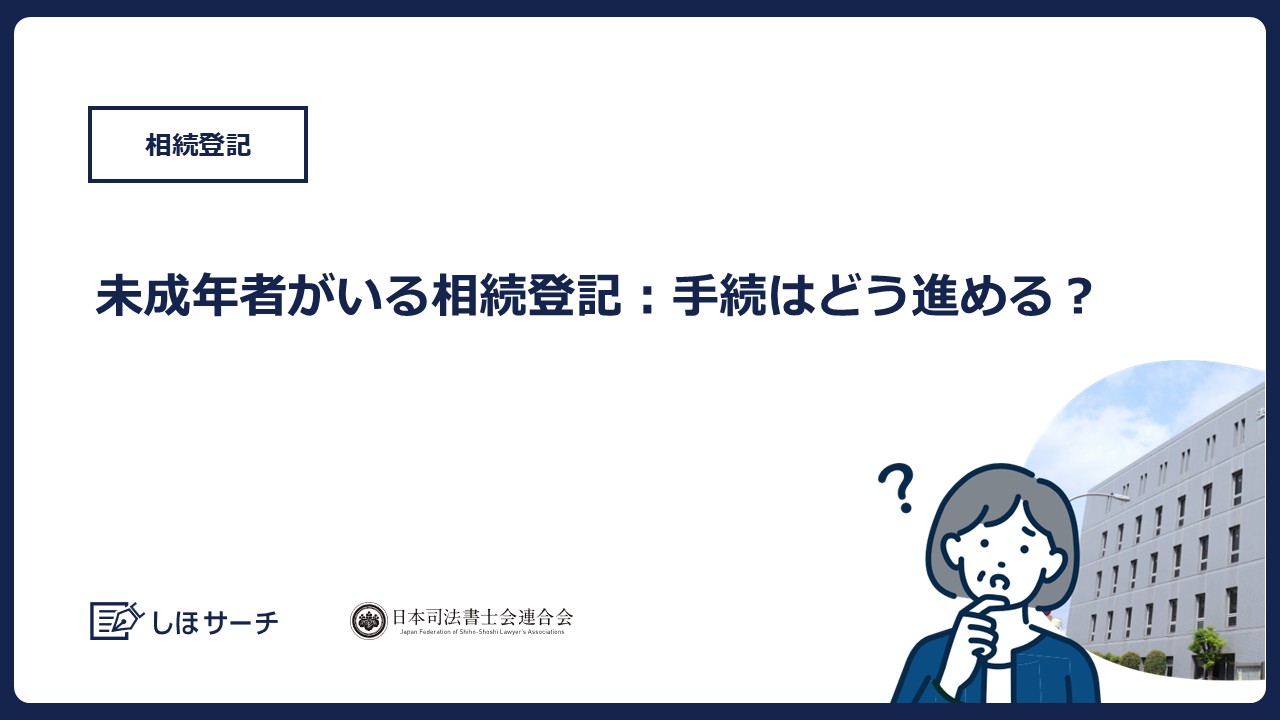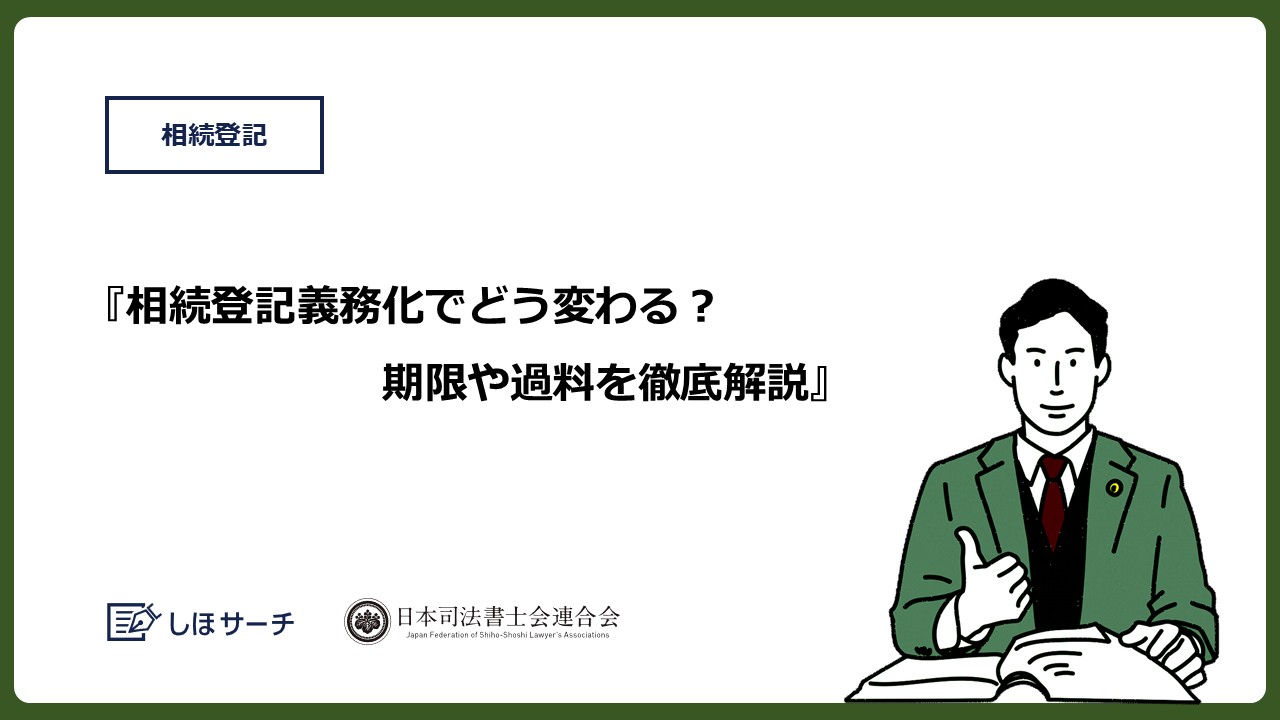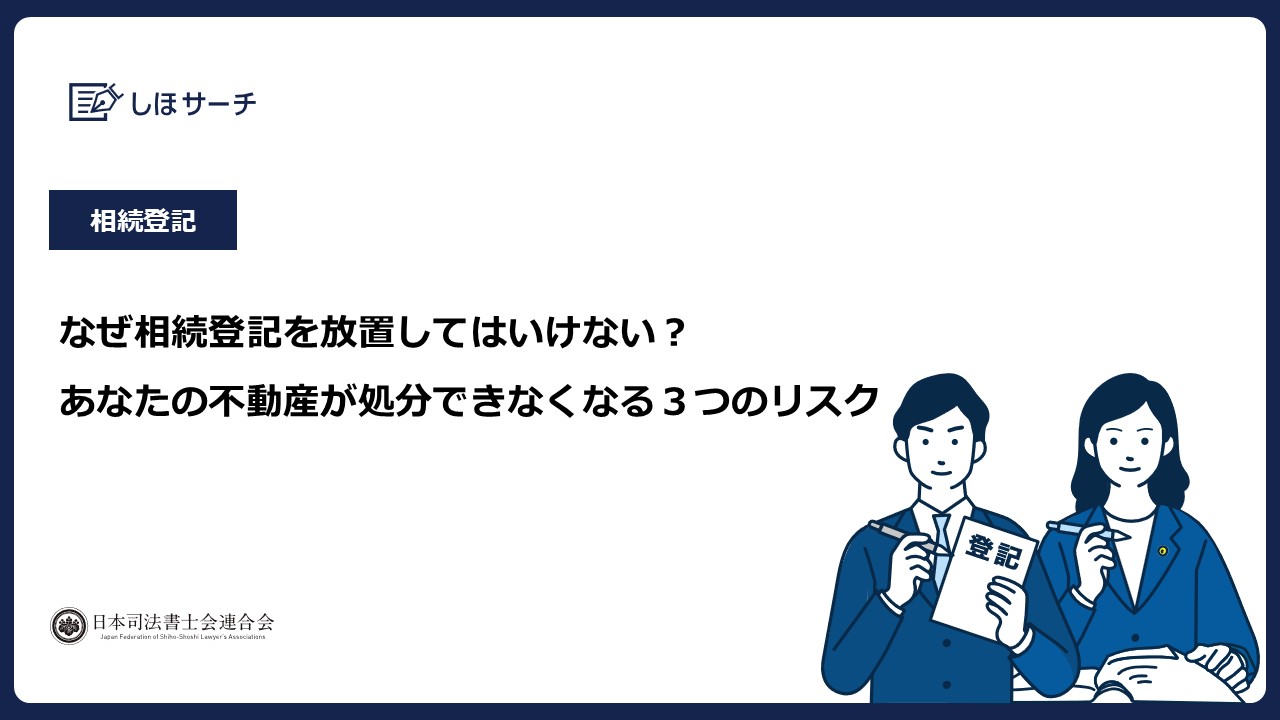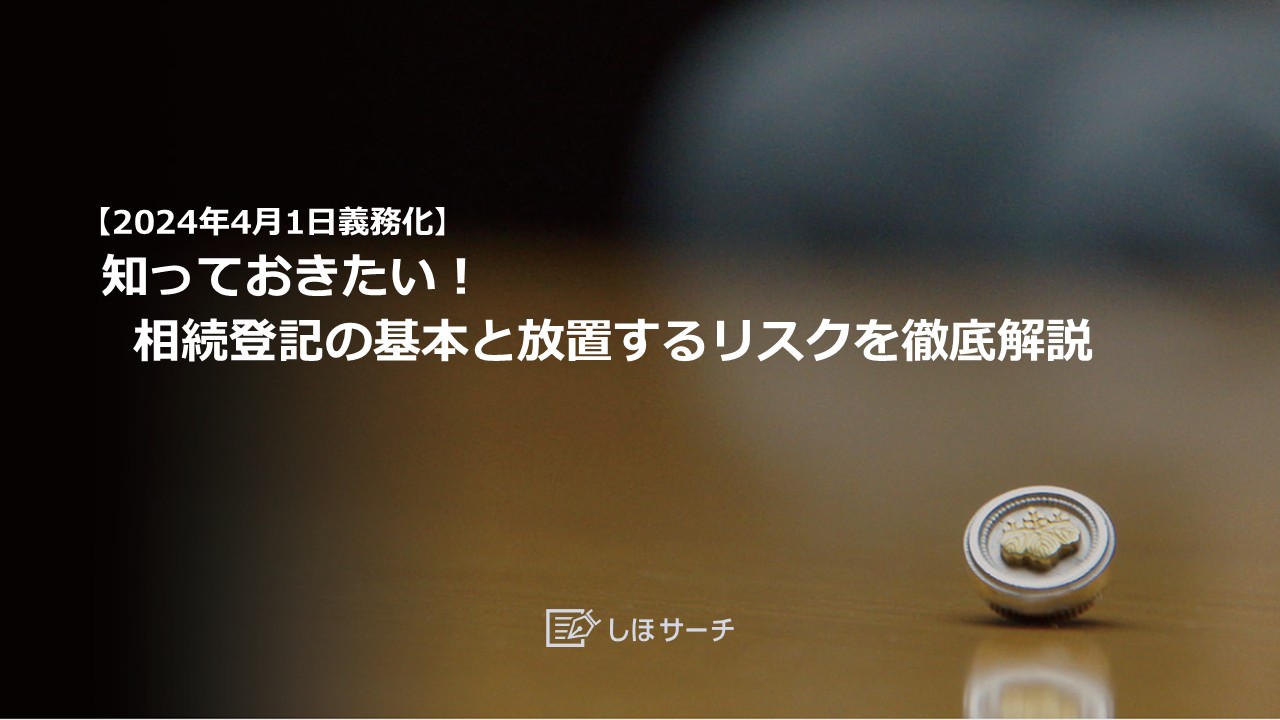相続人の誰かに特定の不動産を相続させたいなら
はじめに
「配偶者に自宅を相続させたい」
「先祖代々の土地は長男に相続させたい」
「同居している子どもに自宅を相続させたい」
「介護をしてくれた長女に不動産を相続させたい」
このように、自分が亡くなった後、相続人の誰かに特定の不動産を相続させたいと考える方は多いのではないでしょうか。
相続は、人が亡くなることで開始します。相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の遺産は、原則として、法律で定められた相続分(法定相続分)の割合で相続人(法定相続人)に承継されます。一般的には、相続人の間で話し合って遺産の分け方を決めることになります。しかし、もし亡くなった方が生前に遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が優先され、遺言書に書いてあるとおりに、遺産を分けることになります。
遺言書が「ない場合」と「ある場合」では、相続手続や遺産の分け方に違いが出てくるのです。
本記事では、相続人の誰かに特定の不動産を相続させる方法として、『遺言書』を作成することが有効な対策であることをご紹介します。
遺言書が「ない場合」と「ある場合」の違い
実際に、どのような違いがあるのか具体例でみていきましょう。
(具体例)
母は、10年前に他界した父から都内の自宅(土地・建物)を相続し、一人で暮らしていました。母には、近くに住む長男と結婚して遠方で暮らす長女の2人の子どもがいます。
母が住む家は老朽化が進み、大規模な修繕か建替えが必要な状況でしたが、母は年金暮らしでその費用がありません。住み慣れた場所から離れたくはありませんでしたが、老朽化した建物で高齢者の一人暮らしが不安でしたし、足腰も弱くなってきたので「自宅を売却して施設に入った方がよいのか」と悩んでいました。そのような中、長男が「自分が実家を建て替えて、母と同居する」と申し出てくれました。長男が実家を建て替え、母は長男家族と同居を開始し、一人暮らしのときよりも安心して、充実した生活を送れるようになりました。母は、日々の生活を支えてくれる長男に感謝し、「この土地は長男に相続させたい」と考えるようになりました。
このような状況で、母が亡くなり相続が発生した場合、「この土地は長男に相続させたい」という母の想いを実現させるためにはどのような手続が必要になるでしょうか?
(なお、ここではわかりやすく比較するために実際に必要となる手続や書類については一部省略して記載しています。)
①【遺言書がない場合】
母が生前に何も準備をしていなかった場合、母の相続人である長男と長女の2人で遺産の分け方を決める話し合い(遺産分割協議)が必要です。遺産分割協議は相続人全員が参加して行う必要があります。
今回の具体例では、長男と長女の2人が「長男が土地を取得する」ことに合意すれば協議自体は成立します。ただし、実際に不動産の名義を母から長男に変更する手続(相続登記)をする場合は、遺産分割協議で決定した内容を書面(遺産分割協議書)に記し、その書面に相続人全員でハンコを押すこと(実印+印鑑証明書)が必要になります。
(手続)
⑴相続人全員で遺産分割協議を行う
⑵遺産分割協議書を作成し、相続人全員がハンコを押す
⑶長男は、遺産分割協議書(+印鑑証明書)を使って、不動産の相続登記を行う
②【遺言書がある場合】
母が生前「遺言者(母)は、東京都△△区○○1番1の土地を長男に相続させる。」という遺言書を作成していた場合はどうでしょうか?
長男は、この遺言書を使って、一人で不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。
遠方に暮らす長女との話し合いや、長女のハンコ(実印+印鑑証明書)は不要です。
(手続)
⑴長男は、遺言書を使って、不動産の相続登記を行う
遺言書がある場合は、不動産を取得する相続人だけで相続登記を行うことができますが、遺言書がない場合は、相続人全員の協力が必要です。遺言書がなくても、遺産分割協議(話し合いや書類の準備)がスムーズに進めば、大きな問題にはならないかもしれません。
しかし、スムーズに進まない場合は、相続手続が一気に大変になる可能性があります。では、どのような場合にスムーズに進まないのでしょうか?
遺産分割協議がスムーズに進まないケースとは?
①相続人間で揉めてしまい、話し合いができない
相続人同士の話し合いで遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所における遺産分割調停や審判手続を通じて遺産の分け方を決めることになります。
②相続人の中に、遺産分割協議に参加できない人がいる
遺産分割協議は法律行為であり、相続人全員が参加する必要があります。そのため、相続人の中に単独で法律行為を行うことができない人(認知症の方や未成年者など)がいる場合や、行方不明の相続人がいる場合は、その人に代わって遺産分割協議に参加する代理人(成年後見人・特別代理人・不在者財産管理人など)を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
③手続に時間と手間がかかる
相続人の数が多い場合や、相続人が多忙で時間が取れない場合、話し合いや書類の準備に時間がかかることがあります。また、相続人が海外に居住している場合は、印鑑証明書の取得ができないため、代わりとなる書類を準備する必要があり、さらに時間と手間がかかります。
スムーズに進まないケースはさまざまな理由で発生し、相続人にとって時間・手間・費用がかかるだけでなく、精神的な負担も大きくなります。このような事態を防ぐためにも、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性がある場合や、残された家族に負担をかけたくないと考える方は、遺言書を作成しておくことが有効な対策といえるでしょう。
※遺言書の有無を確認する方法は、本サイト別記事『遺言書があるかどうすればわかりますか?』(https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/column/013/)をご参照ください。また、相続人の中に未成年者や海外居住者がいる場合の詳細についても、本サイト別記事を「相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議」(https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/column/019/)、「相続人の中に海外居住者がいる場合はどうしたらよいか」(https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/column/016/)をご参照ください。
遺言書とは?
①遺言書とは?
遺言書とは、亡くなった人の最終の意思を示す大切なものです。遺言者が生前に、自分の財産を誰に、どの財産を、どれだけ相続させたいかを指定し、その指定に法的効力を持たせるものです。この指定は法定相続分に優先します。
遺言書は、15歳以上で遺言能力(遺言の内容やその結果を理解できる能力)があれば作成できます。遺言書には主に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つの種類があります。それぞれメリット・デメリットがあるため、自分の状況や目的に合った種類を選んで作成するとよいでしょう。
②遺言書があれば大丈夫?
・使えない遺言書
遺言書は遺言者が生きているうちに作成しますが、その効力が発生するのは遺言者が亡くなった後です。そのため、内容を確認したくても、その時には遺言者本人はいません。このため、遺言書の作成方式は法律で厳格に定められており、法的要件を満たさない遺言書(形式的不備のある遺言書)は無効となります。また、形式に問題がなくても、内容が不明瞭な場合には、相続手続で使用できないことがあります。
さらに、遺言書に記載されていない財産については、遺言書のみでは相続手続ができません。このように、「使えない遺言書」の場合は、最終的に遺産分割協議が必要となるため、せっかく作成した遺言書が活用されないリスクがあります。
③遺留分とは?
遺言書がある場合、基本的には遺言の内容が優先されます。しかし、「遺留分」を侵害している場合、遺言書どおりの相続が実現しない可能性があります。
遺留分とは、一定の相続人(兄弟姉妹を除く法定相続人)に保障された、最低限相続できる遺産の割合のことです。遺留分を侵害された相続人には、侵害された分に相当する金銭を、遺産を多く受け取った人に請求する権利(遺留分侵害額請求)があります。請求された側は、たとえ遺言書があったとしても、遺留分の請求には応じなければなりません。
なお、遺留分を侵害する遺言書は無効でしょうか?いいえ、無効にはなりません。遺留分を侵害していても、形式的な要件を満たしていれば遺言書自体は有効です。遺留分を請求するかどうかは、侵害された相続人の判断に委ねられています。
そのため、遺留分で揉めそうな場合は、最初から遺留分を侵害しない遺言内容にすることや遺留分を請求されても問題が生じないような対策を講じておくといった配慮が重要です。
遺言書を作成する際は、法律上の要件を守り、内容や遺留分にも十分配慮することが重要です。そのため、専門家に相談しながら作成することをおすすめします。
※遺言書の詳細については、本サイト別記事「あって良かった遺言書」(https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/column/002/)をご参照ください。
不動産を相続したら「相続登記」が必要です
「相続登記」とは、相続によって取得した土地や建物の名義を、被相続人から相続人へ変更する手続のことです。名義変更を行うには、法務局(登記所)に相続登記を申請する必要があります。相続登記の申請は、不動産を取得した相続人が行います。 なお、司法書士にご依頼いただくことで、代理申請も可能です。
①相続登記が対抗要件
「遺言者は、東京都△△区○○1番1の土地を長男に相続させる。」
このように、特定の遺産を特定の相続人に相続させることを指定する遺言書を「特定財産承継遺言」といいます。
従来は、「不動産を相続させる」という内容の遺言書がある場合、相続発生と同時に不動産の所有権が指定された相続人に当然に移転し、相続登記をしなくても第三者に対して自らの権利を主張できるとされていました。
しかし、2019年(令和元年)7月1日施行の民法改正により、たとえ遺言書があったとしても、自己の法定相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者に対して権利を主張できないと変更されました。
なお、この改正は、遺言による不動産の取得だけでなく、遺産分割協議による不動産の取得の場合にも適用されます。そのため、相続により不動産を取得した方は、その権利を守るためにも速やかに相続登記を行うことが重要です。
②相続登記の申請義務化
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。この義務化は、2024年4月1日以降に発生する相続だけでなく、過去の相続にも適用されます。
相続登記の期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内と定められています。正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。そのため、不動産を相続した方は、速やかに相続登記を済ませましょう。
まとめ
司法書士は、相続登記のご依頼を受ける中で、「遺言書があれば、こんなに大変(時間・手間・費用・精神的負担)な思いをせずに済んだのではないか」と感じるケースにしばしば遭遇します。実際に、「知っていれば、遺言書を作成してもらっていたのに」と後悔する方も少なくありません。相続は誰にでも訪れるものであり、あらかじめ対策をしておくことが大切です。
しかし、「自分は相続対策をすべきなのか分からない」「遺言書を作成したいが、何から始めればよいのか分からない」と悩まれる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、特定の不動産を特定の相続人に相続させる方法として、主に遺言書の作成について解説しました。ただし、ケースによっては、生前贈与や家族信託など、別の方法を検討したほうがよい場合もあります。
相続や遺言書に関して疑問や不安がある場合は、まずは「しほサーチ」で最寄りの司法書士を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。