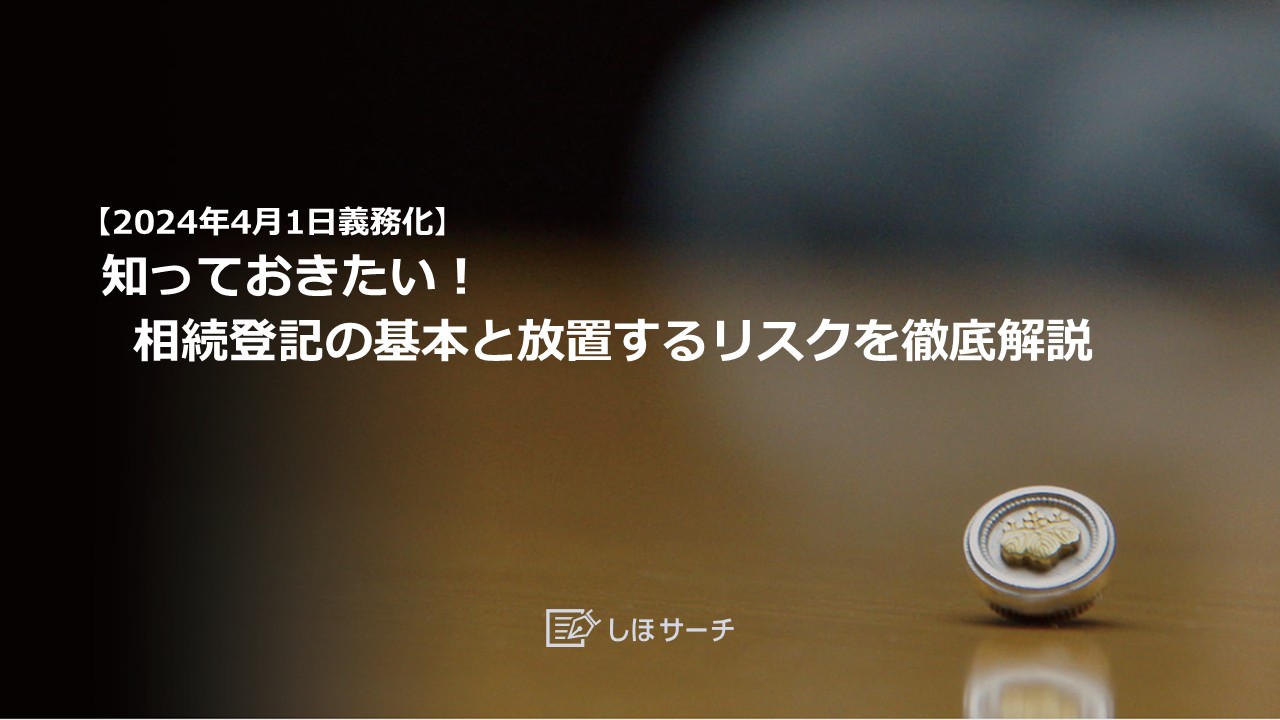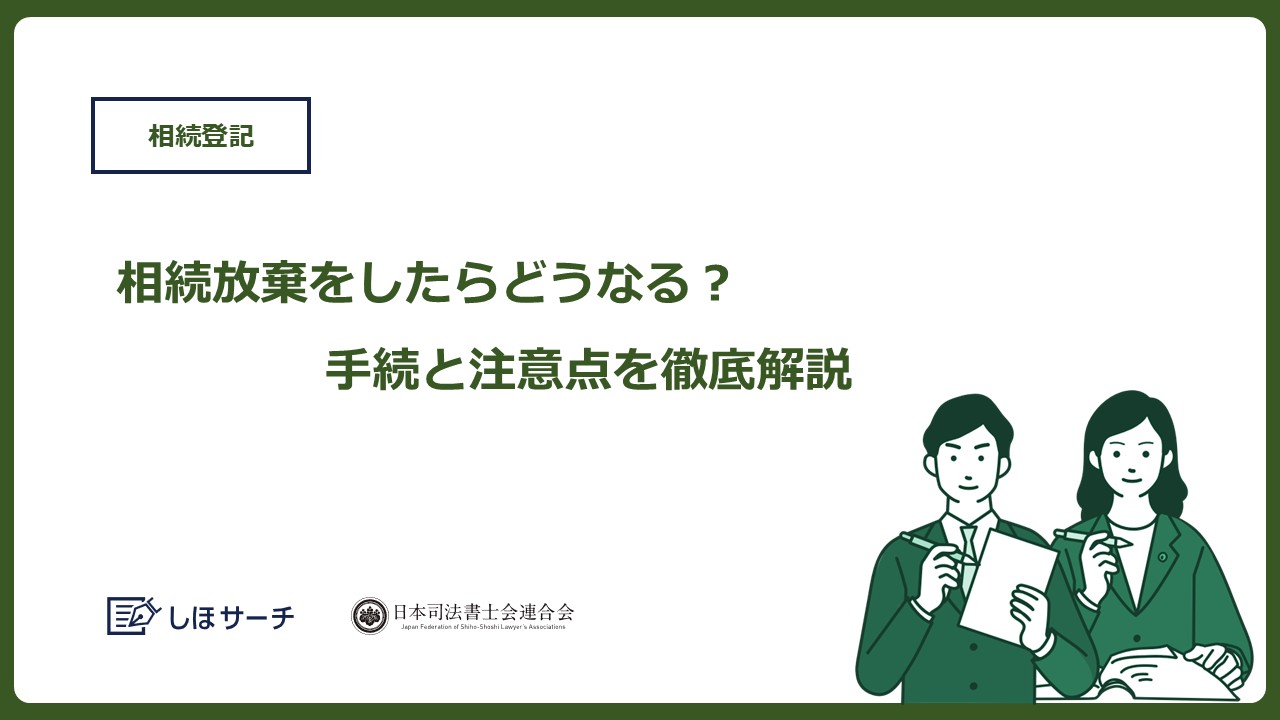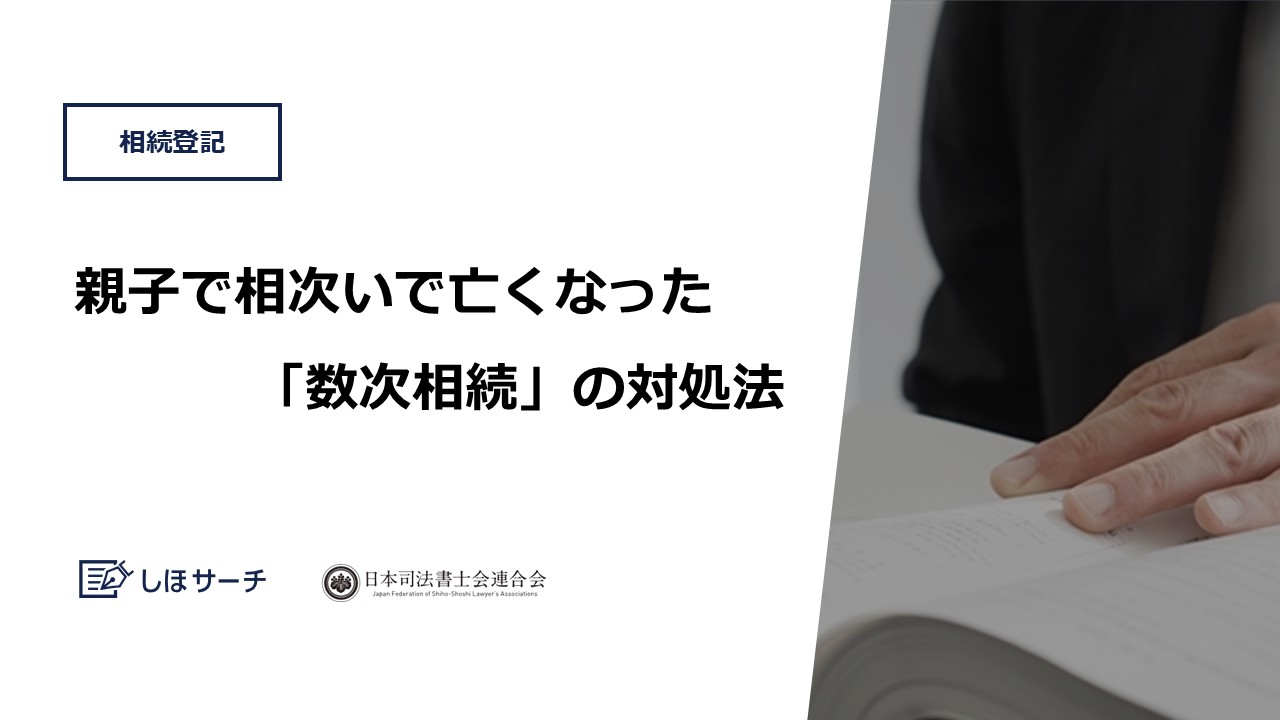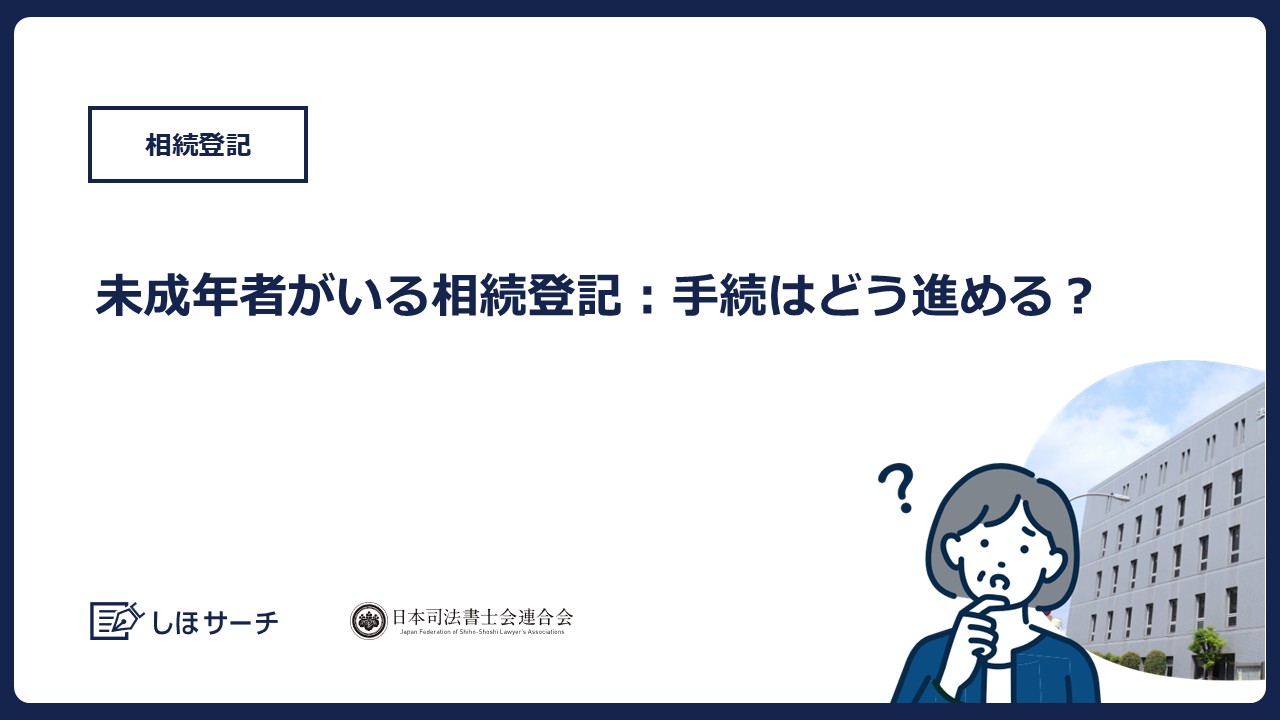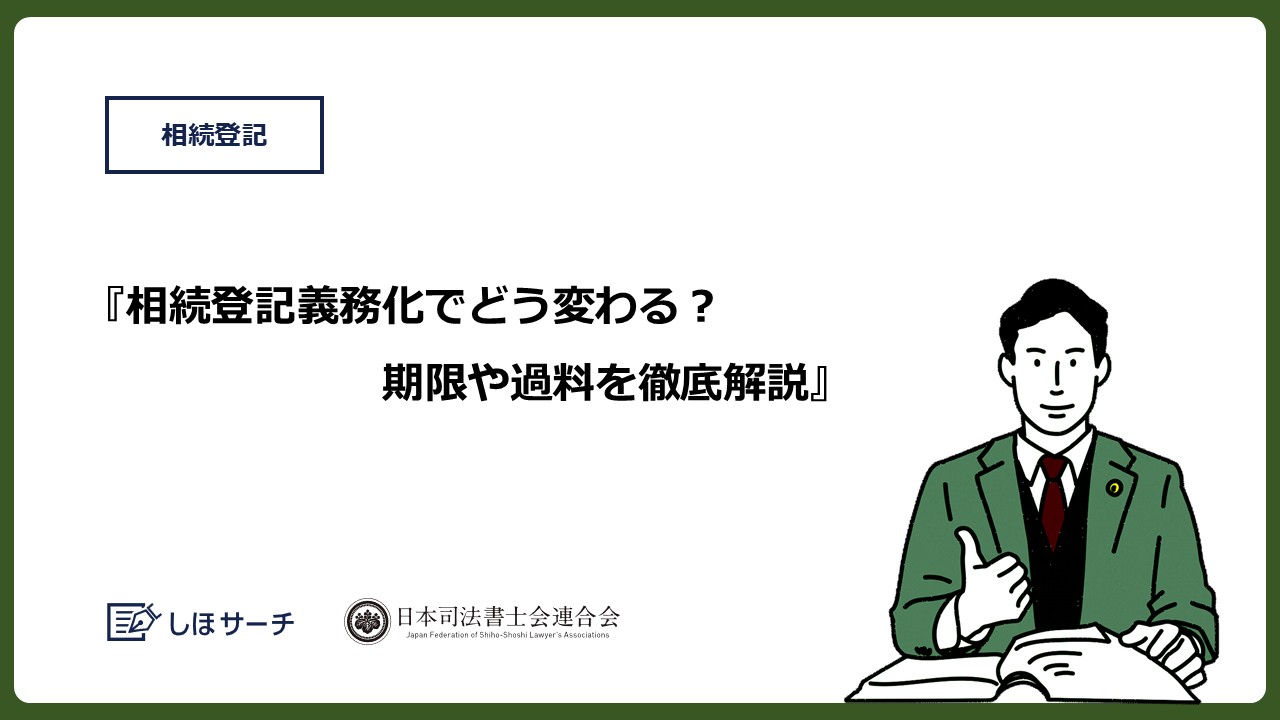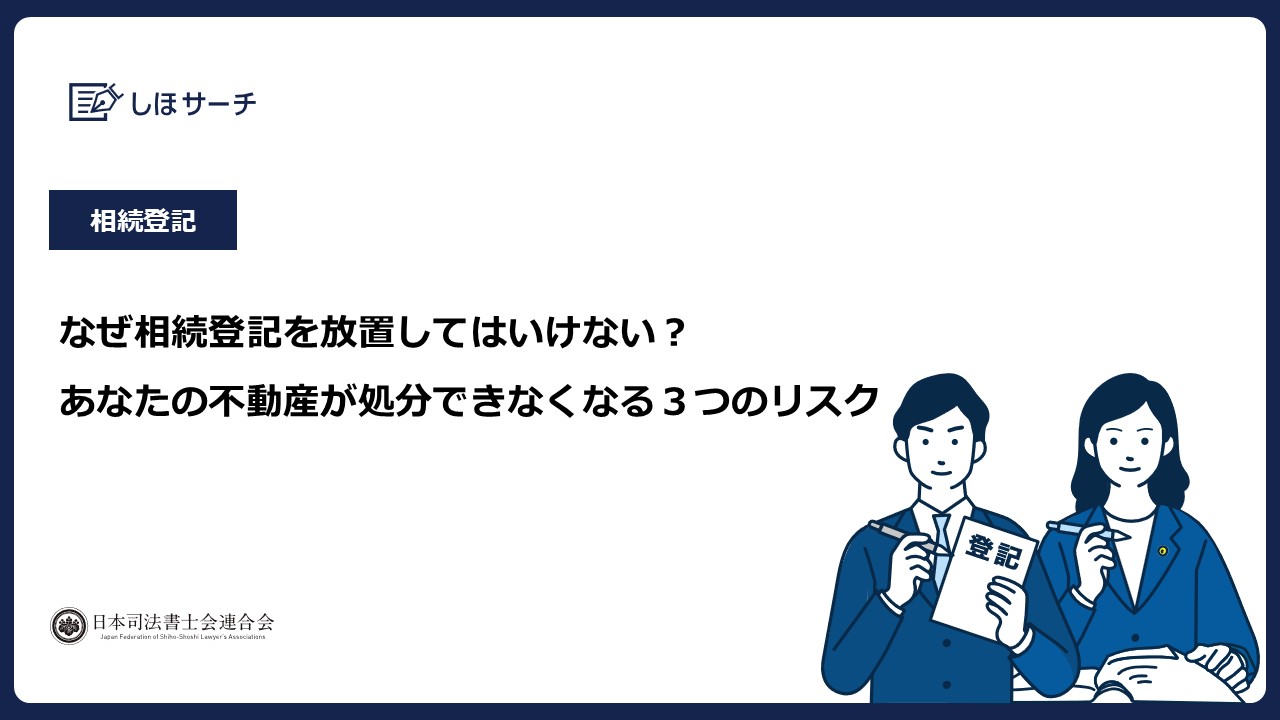【2024年4月1日義務化】知っておきたい!相続登記の基本と放置するリスクを徹底解説
- 目次
- 第1章:何がどう変わった?相続登記の申請義務化の3つのポイント
- ポイント1:相続登記が「義務」になりました
- ポイント2:過去の相続も対象です(遡及適用)
- ポイント3:正当な理由なく怠ると「過料」の対象に
- なぜ、相続登記は義務化されたのか?
- 第2章:過料だけじゃない!相続登記を放置する本当のリスク
- リスク1:不動産を売りたいときに売れない、貸せない
- リスク2:時間が経つほど権利関係が複雑化する
- リスク3:他の相続人の持分を差し押さえられる
- 第3章:相続登記の手続と司法書士の役割
- 第4章:知っておきたい!義務化に伴う2つの新制度
- 1. 相続人申告登記
- 2. 所有不動産記録証明制度
- まとめ:相続登記は「いつか」ではなく「いま」
「親から実家を相続したけれど、手続が面倒でそのままにしている」
「先祖代々の土地があるらしいが、誰の名義になっているかよくわからない」
このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。これまで任意だった不動産の相続登記が、2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。この法律の改正は、過去に発生した相続にも適用されるため、多くの方にとって無関係ではありません。
「自分には関係ない」と思っていた方も、この記事を読めば、なぜ今、相続登記が必要なのか、そして放置するとどのような不利益があるのかをご理解いただけるはずです。
この記事では、相続登記の専門家である司法書士が、新しい制度の基本から手続の流れ、そして知っておきたいポイントまで、わかりやすく解説します。大切な資産を守り、次の世代へ円滑に引き継ぐために、ぜひ最後までお読みください。
第1章:何がどう変わった?相続登記の申請義務化の3つのポイント
まずは、今回の法律の改正で何がどう変わったのか、最も重要な3つのポイントから確認していきましょう。
ポイント1:相続登記が「義務」になりました
これまで、相続した不動産の名義変更(相続登記)をするかどうかは、個人の判断に委ねられていました。しかし、2024年(令和6年)4月1日以降は、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務となります。
いつまでに?:不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
誰が?:不動産を相続した相続人
例えば、2024年5月1日にご家族が亡くなり、同日、ご自身が不動産を相続することを知った場合、2027年5月1日までに相続登記を申請しなければなりません。
ポイント2:過去の相続も対象です(遡及適用)
「義務化が始まる前の相続だから、自分には関係ない」とお考えの方、注意が必要です。
今回の相続登記の申請義務化は、法律が施行される2024年4月1日より前に発生した相続にも適用されます。
そのため「何十年も前に亡くなった祖父名義の土地」なども、対象に含まれるのです。
過去の相続については、2024年4月1日又は自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内、つまり早ければ2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。長い間手続をしていなかった方は、早急な対応が求められます。
ポイント3:正当な理由なく怠ると「過料」の対象に
定められた期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
もちろん、やむを得ない事情がある場合は考慮されます。例えば、以下のようなケースは「正当な理由」として認められる可能性があります。
・相続人が非常に多く、戸籍謄本等の収集や連絡に時間がかかる
・遺言の有効性をめぐって裁判で争っている
・相続人に重病の方がいる
・相続した不動産が遠隔地にあり、調査に時間がかかる
ただし、単に「手続が面倒だった」「費用を払いたくなかった」といった理由は、正当な理由として認められません。過料は行政罰であり、刑事罰のような前科がつくものではありませんが、負担となることは間違いありません。
なぜ、相続登記は義務化されたのか?
そもそも、なぜ国は法律を改正してまで相続登記の申請を義務化したのでしょうか。
その背景には、「所有者不明土地問題」という深刻な社会問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿を確認しても所有者が誰だかすぐにわからない、または所有者がわかっても連絡を取ることができない土地のことです。相続登記がされないまま何世代にもわたって放置された結果、相続 人がネズミ算式に増え、現在の所有者を特定することが極めて困難になっているのです。
このような土地は、国土全体の約24%を占めるともいわれ、次のような問題を引き起こしています。
・公共事業の阻害:道路の拡幅やインフラ整備を進めようとしても、土地の所有者がわからず、用地買収が進まない。
・災害復旧の遅れ:豪雨や地震で被災した地域の復旧工事が、所有者不明土地の存在によって妨げられる。
・周辺環境の悪化:土地が管理されずに放置され、雑草が生い茂ったり、不法投棄の温床になったりする。
・民間取引の停滞:周辺の土地を含めた再開発や、個人の売買がスムーズに進まない。
これらの問題を解決し、土地の利用を促進するために、相続登記の申請を義務化して不動産の所有者を明確にすることが不可欠となったのです。
第2章:過料だけじゃない!相続登記を放置する本当のリスク
相続登記の申請義務化は、10万円以下の過料に注目が集まりがちです。しかし、本当のリスクは、それ以前から存在していた「相続登記をしないことによるデメリット」です。
リスク1:不動産を売りたいときに売れない、貸せない
最も大きなデメリットは、不動産を自由に処分(売却、贈与、賃貸など)したり、担保に入れて融資を受けたりすることができない点です。
例えば、相続した実家を売却して、老人ホームの入居費用に充てたいと考えたとします。しかし、亡くなった親の名義のままでは、買主への所有権移転登記ができません。売却の前提として、まずご自身の名義に相続登記を済ませる必要があります。
いざ売却しようというタイミングで相続登記を始めると、相続人の調査や書類の収集に予想以上の時間がかかり、絶好の売却機会を逃してしまう可能性もあります。
リスク2:時間が経つほど権利関係が複雑化する
相続登記をしないうちに、相続人の誰かが亡くなってしまうと、その人の相続権はさらにその法定相続人へと引き継がれます(これを数次相続といいます。)。
例えば、当初の相続人が兄弟3人だけだったとしても、長男が亡くなればその配偶者と子どもたち、次に次男が亡くなればその配偶者と子どもたち…というように、関係者はどんどん増えていきます。
時間が経てば経つほど、会ったこともない親戚や、連絡先もわからないような遠い親族が登場し、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)は極めて困難になります。全員の実印と印鑑証明書がなければ不動産の名義変更はできず、たった一人の協力が得られないだけで、手続は頓挫してしまいます。
リスク3:他の相続人の持分を差し押さえられる
遺産分割協議がまとまる前でも、各相続人は自分の「法定相続分」に応じた持分を登記することができます。もし、相続人の誰かに多額の債務があり、その債権者(お金を貸した側)がその相続人の持分を差し押さえてしまうと、事態はさらに複雑になります。
差し押さえられた持分が競売にかけられ、見知らぬ第三者が共有者として不動産の権利関係に入り込んでくる可能性もゼロではありません。そうなると、その不動産を売却することも、住み続けることも難しくなってしまうおそれがあります。
第3章:相続登記の手続と司法書士の役割
では、実際に相続登記はどのように進めればよいのでしょうか。
ここでは、基本的な手続の流れと、専門家である司法書士に依頼するメリットについて解説します。
相続登記は、一般的に以下のステップで進みます。
・遺言書の有無を確認する
・必要書類を収集する
・相続人を確定する
・遺産分割協議を行う
・法務局へ登記を申請する
ご覧いただいたように、相続登記には専門的な知識と多くの時間・労力が必要です。特に、戸籍の収集や法律に基づいた書類の作成は、慣れていない方にとっては非常に煩雑に感じられるでしょう。
そこで頼りになるのが、登記の専門家である司法書士です。
司法書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。
・正確かつ迅速な手続
・時間と手間の大幅な削減
・ワンストップでの対応
・精神的な安心感
登記に必要な登録免許税等の費用や司法書士への報酬は発生しますが、手続の煩雑さや将来起こりうるトラブルのリスク回避を考えれば、司法書士に依頼するメリットは非常に大きいといえるでしょう。
第4章:知っておきたい!義務化に伴う2つの新制度
1. 相続人申告登記
「3年以内に遺産分割協議がまとまりそうにない」「相続人が多すぎて、すぐに登記申請の準備ができない」
このような場合に利用できるのが「相続人申告登記」制度です。
これは、遺産分割が成立する前に、自分が相続人の一人であることを法務局に申し出ることにより、ひとまず相続登記の義務を果たしたとみなされる手続です。
2. 所有不動産記録証明制度
「亡くなった親が、どこにどれだけ不動産を持っていたか正確にわからない」
このような場合に便利なのが、2026年(令和8年)2月2日から始まる「所有不動産記録証明制度」です。
所有不動産記録証明制度を利用すれば、特定の人が登記上の名義人となっている不動産を、全国の法務局から検索し、一覧で証明書として発行してもらうことができます。これにより、相続財産の調査が以前よりも格段に容易になることが見込まれます。
まとめ:相続登記は「いつか」ではなく「いま」
2024年4月1日から始まった相続登記の申請義務化は、私たち一人ひとりが不動産の所有者としての責任を改めて考えるきっかけとなるものです。
「まだ3年の猶予がある」と先延ばしにしていると、いざという時に手続が間に合わなかったり、権利関係が複雑化して思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。
相続は、誰にでも起こりうることです。そして、その手続は、早ければ早いほど、関係者の負担は少なくて済みます。この記事を読んで少しでも不安を感じた方は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。
私たち司法書士は、相続登記の専門家として、皆様の大切な資産とご家族の想いを、円滑に次の世代へとつなぐお手伝いをさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
あなたの、そしてご家族の未来のために、相続登記について「いま」一歩踏み出してみませんか。