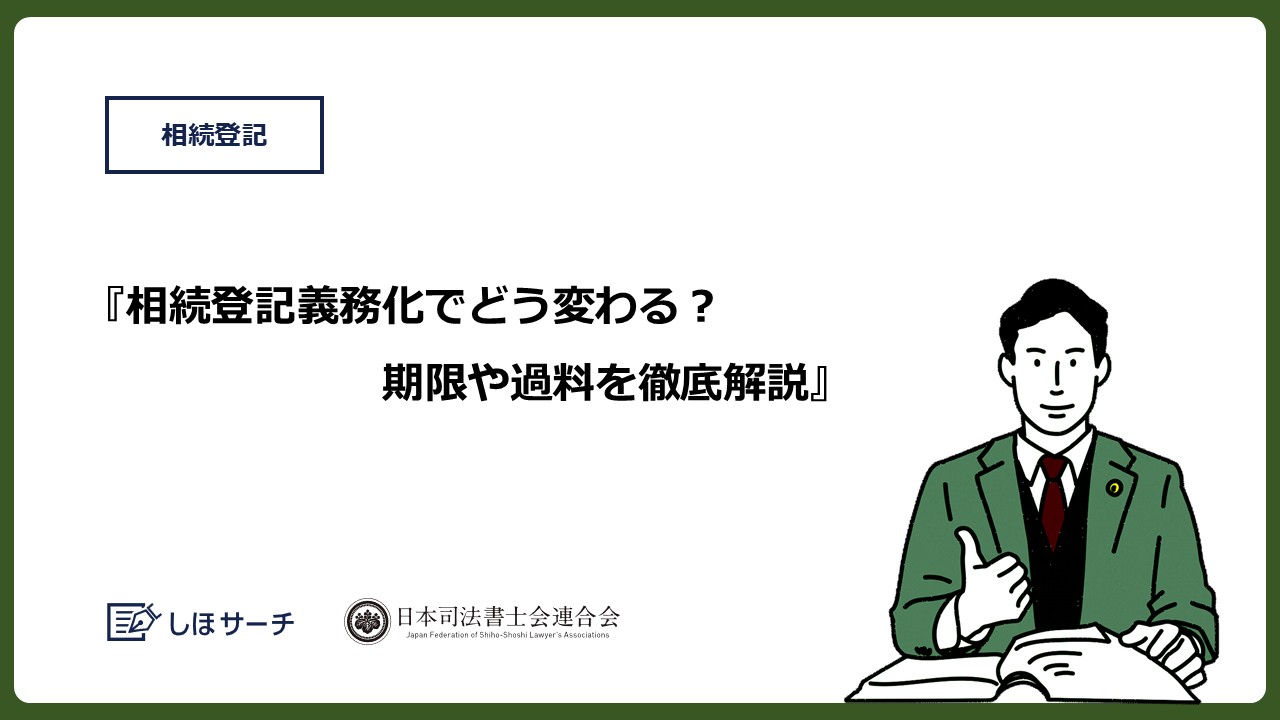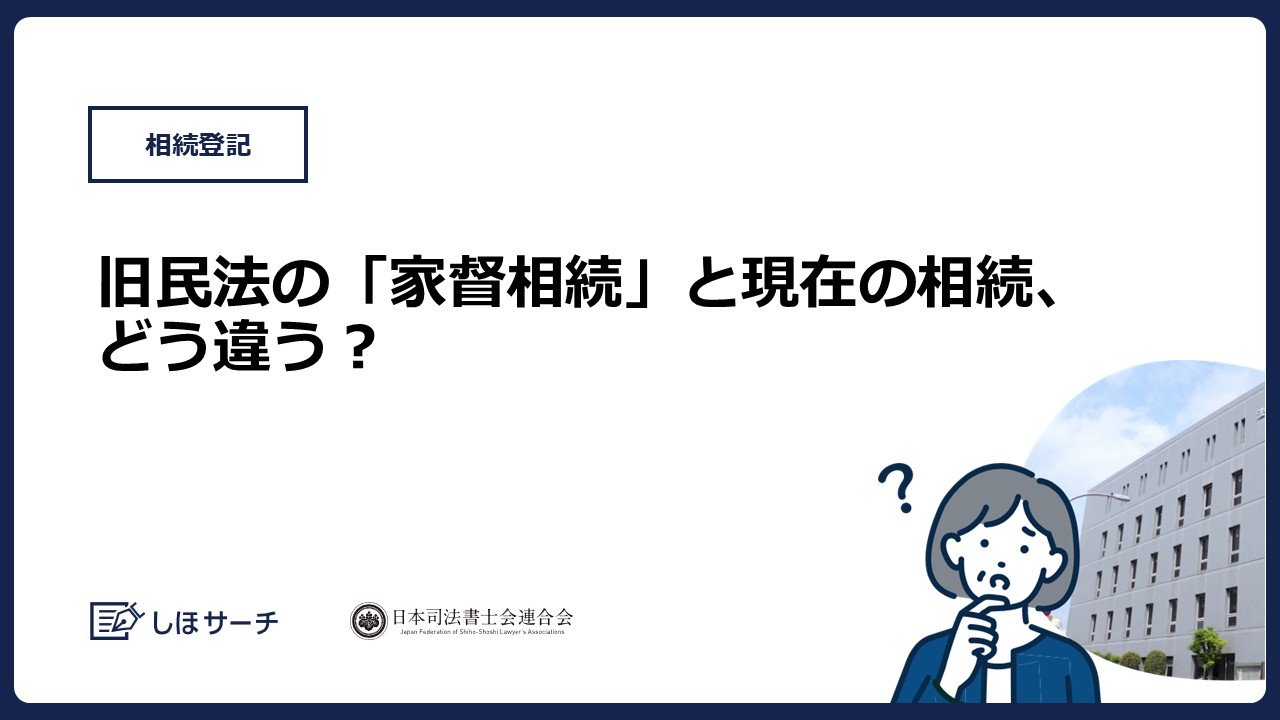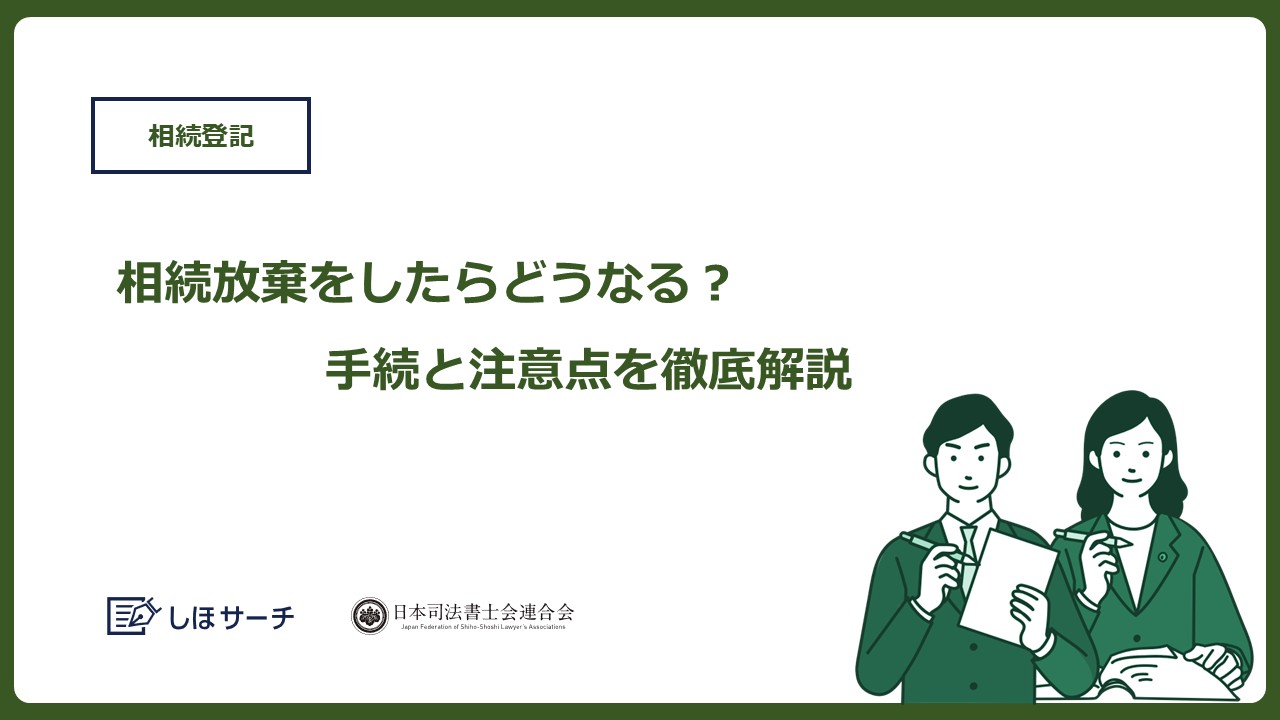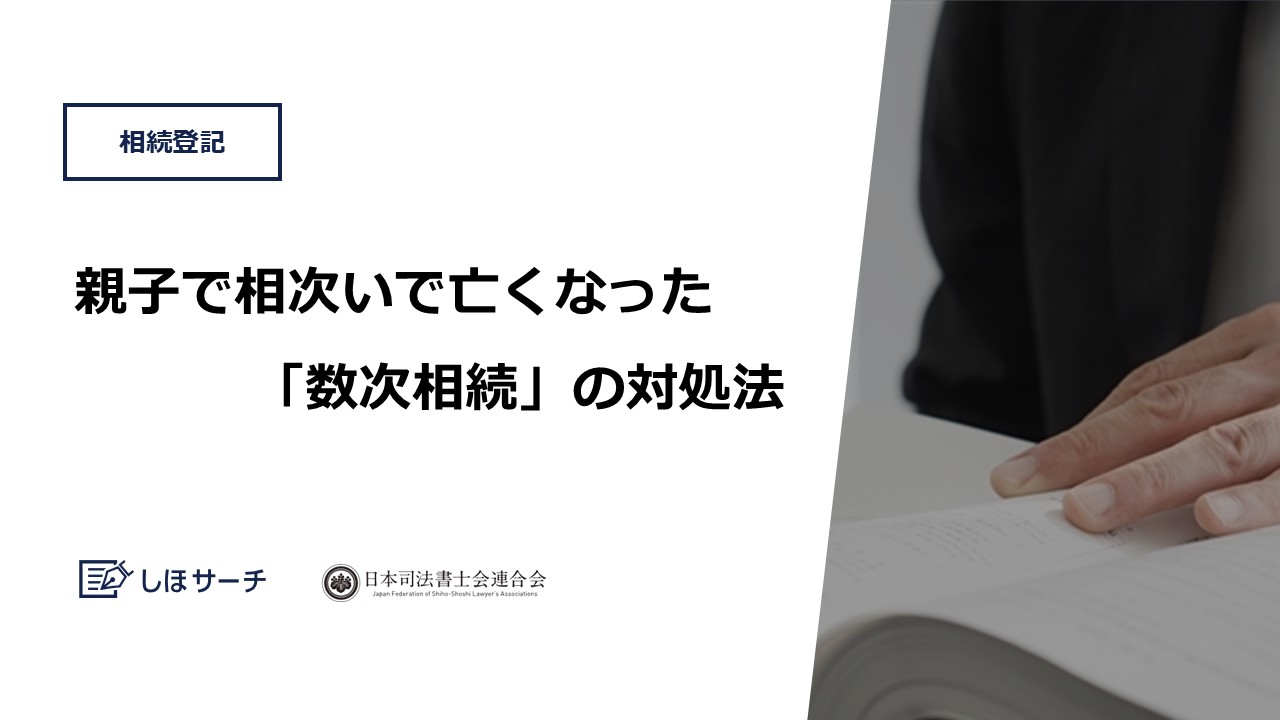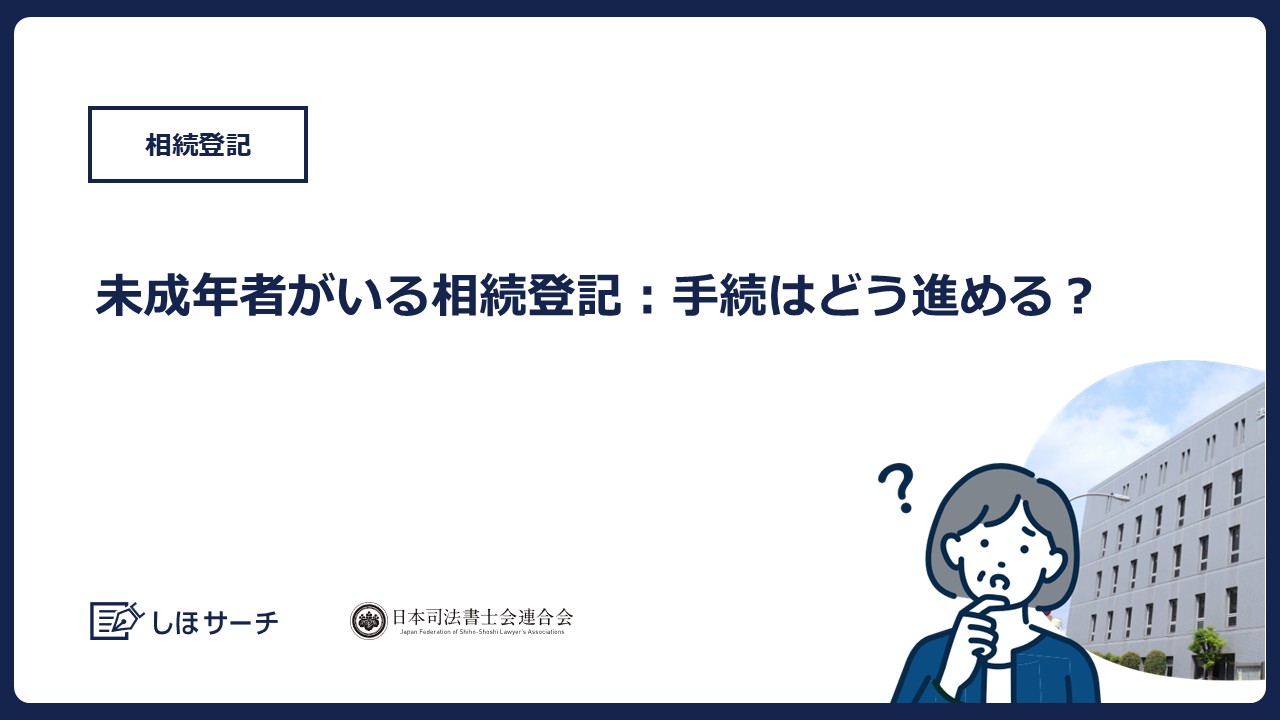『相続登記義務化でどう変わる? 期限や過料を徹底解説』
相続登記の申請義務化は2024年(令和6年)4月1日から始まり、これによって申請期限と過料が新たに設けられました。
主な変更点は次の2つです。
申請期限(いつまでに?)
原則として、「相続を原因として不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。
〇遺産分割協議が成立した場合
3年以内に遺産分割協議が成立しないときは法定相続分に基づく登記申請をするか、相続人である旨の申出(相続人申告登記)をする必要があります。遺産分割協議(相続人間での話し合い)が成立した場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に基づいた登記申請が必要です。
〇施行日(2024年4月1日)より前の相続について
相続登記の申請義務化より前に発生した相続(過去の相続)も対象となります。この場合、「2027年(令和9年)3月31日まで」(施行日から3年間の猶予期間)か、「相続を原因として不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内の、いずれか遅い日までに登記する必要があります。
これを具体的なケースに当てはめてみます。
ケースA:遺言がなく、法定相続する場合
通常は、「被相続人(亡くなった方)が亡くなったこと」と「自分が相続人であり、その不動産が遺産に含まれていること」の両方を知った日が起算点となります。
例えば、親が亡くなり、その親が建物を所有していたことを知っていれば、通常はその死亡日から3年以内となります。
ケースB:遺産分割協議で不動産を取得した場合
相続が発生しても、すぐに誰がその不動産を取得するのか決まらないことも多くあります。
その後、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、「この不動産は長男が取得する」などと決まった場合、その遺産分割協議が成立した日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
※この場合、ケースAの「3年」と、ケースBの「3年」の二段階の義務が発生する点に注意が必要です。遺産分割協議がまとまらない場合、ひとまず法定相続分での登記(または後述の「相続人申告登記」)を3年以内に行う必要があります。
ケースC:遺言で不動産を取得した場合
遺言によって特定の人が不動産を取得した場合も、原則としてケースAと同様、「亡くなったこと」と「遺言で自分が不動産を取得すること」を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
過料(しなかったらどうなる?)
正当な理由がないにもかかわらず上記の期限内に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。過料は行政上のペナルティであり、刑事罰ではないため、いわゆる「前科」はつきません。ただし、過料を支払ったとしても、登記申請の義務がなくなるわけではありません。
過料についても、いくつか重要なポイントがあります。
〇「正当な理由」があれば過料は科されない
期限内に相続登記の申請ができないことについて「正当な理由」があると認められれば、過料は課されません。 法務省が示している「正当な理由」の例としては、以下のようなものがあります。
・相続人が非常に多く、戸籍謄本の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合。
・遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある場合。
・登記申請義務を負う相続人自身が、重病などで登記申請を行えない場合。
・経済的に困窮しており、登記費用(登録免許税など)を支払うのが難しい場合。
※ただし、単に「忙しいから」「手続が面倒だから」といった理由は正当な理由とは認められにくいものと思われます。
〇いきなり過料が科されるわけではない
期限(3年)を過ぎたら即座に10万円の過料が請求されるというわけではありません。手続の流れは以下のようになると想定されています。法務局(登記官)が、登記されていない不動産を発見した場合、まず相続人に登記申請をするよう「催告」を行います。催告を受けてもなお、正当な理由なく登記申請を行わない場合、登記官は裁判所に対してその旨を通知します。通知を受けた裁判所が、事情を聴取した上で過料を科すかどうか、またその金額(10万円の範囲内)を決定します3
〇期限に間に合わない場合の救済制度
もし3年以内に遺産分割協議がまとまらないなどの事情がある場合、新しく設けられた「相続人申告登記」という制度を利用することができます。これは、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出ることで、ひとまず登記申請義務を果たしたとみなされる簡易的な手続です。ただし、これは暫定的な措置であり、最終的に遺産分割が成立したら、その日から3年以内に正式な相続登記の申請を行う必要があります。
過去の相続(相続登記の申請義務化施行前の相続)の扱い
2024年4月1日より前に発生した相続(例えば、10年前に亡くなった親名義のままの不動産)も、すべて相続登記の申請義務化の対象となります。この場合、慌てて登記する必要がないよう、3年間の猶予期間が設けられています。具体的には、2027年3月31日までに相続登記の申請を行えば、義務を果たしたことになり、過料の対象にはなりません。
救済措置「相続人申告登記」
もし、「3年以内に遺産分割協議がまとまりそうにない」あるいは「ひとまず義務だけは果たしておきたい」という場合のために、「相続人申告登記」という新しい制度ができました。これは、「私がこの不動産の相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの簡易的な手続です。相続人申告登記の申出を3年以内に行えば、その時点で相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。ただし、これは「誰が不動産を取得したか」を登記するものではないため、この申出だけでは不動産の処分等を行うことはできません。最終的に遺産分割協議が成立したら、その日から3年以内に、改めて正式な相続登記(名義変更)の申請を行う必要があります。ご不明な点があれば、最寄りの司法書士にご相談ください。