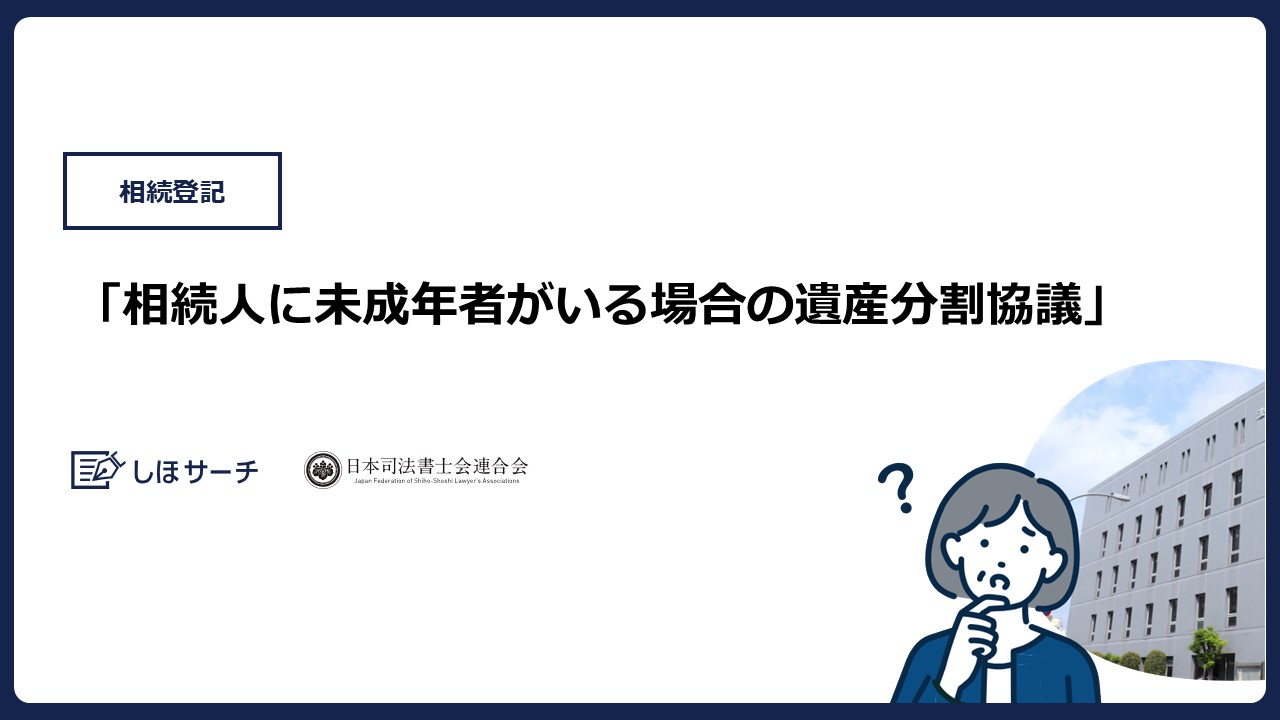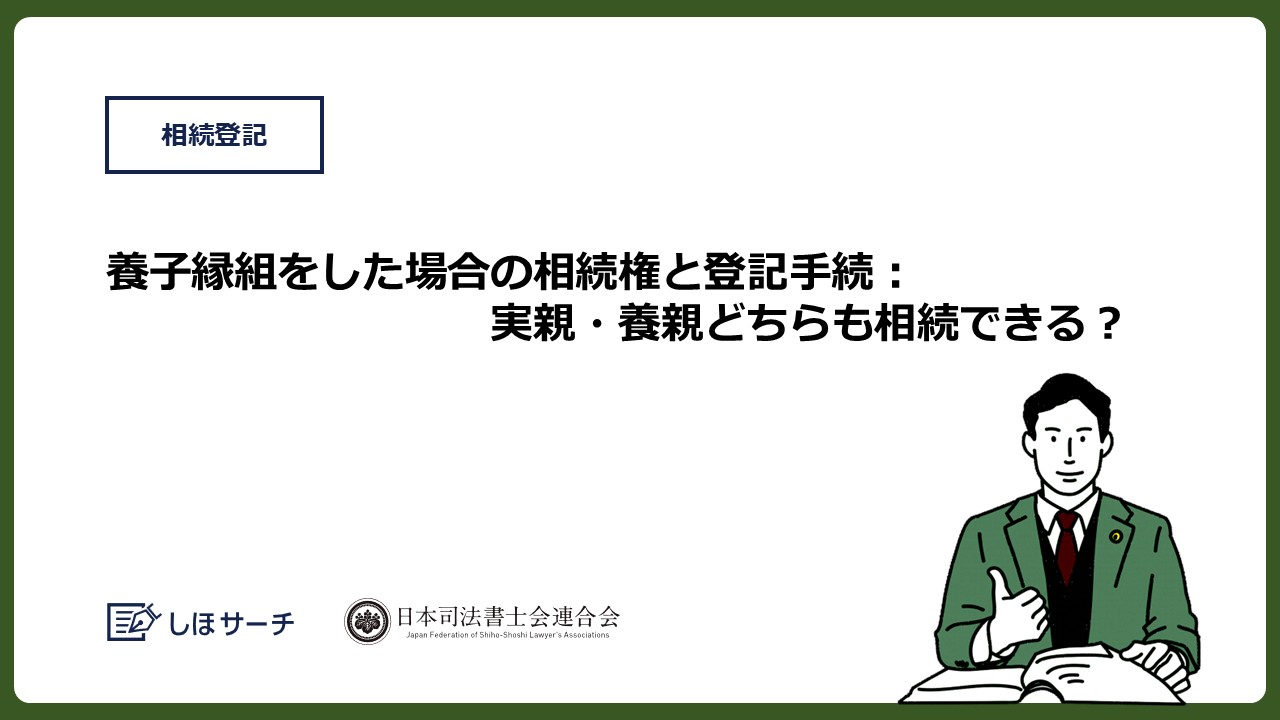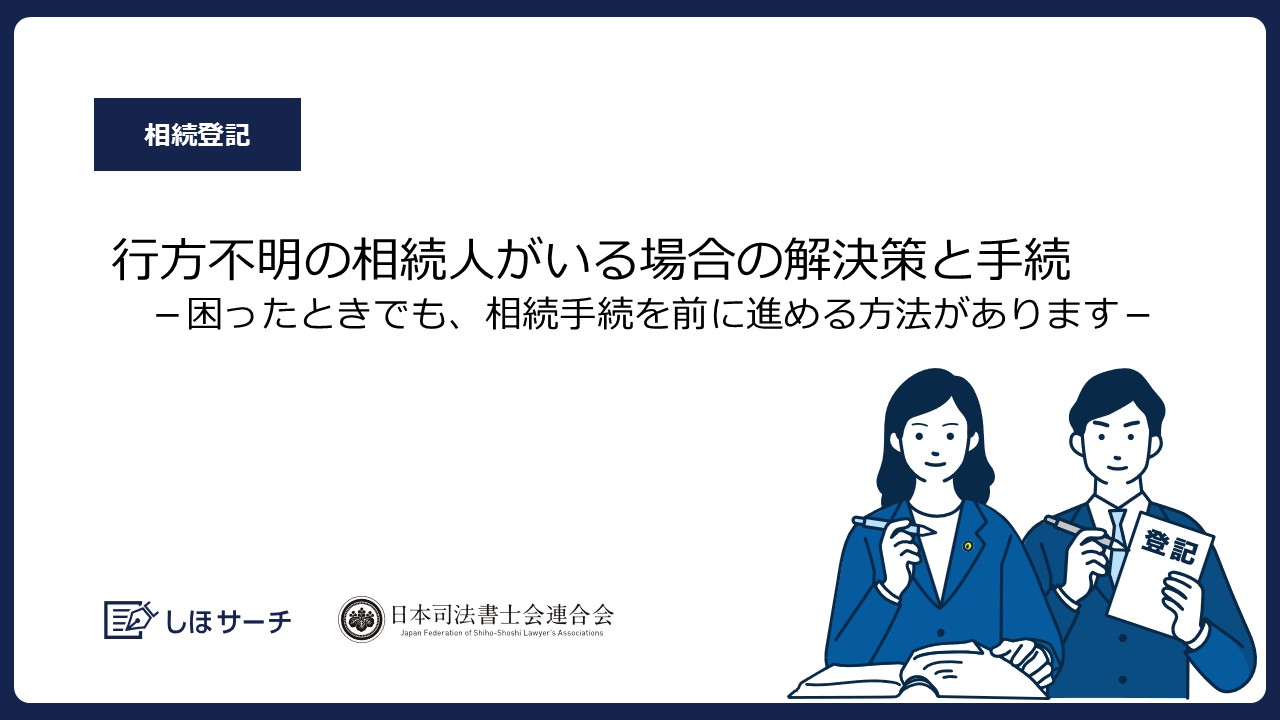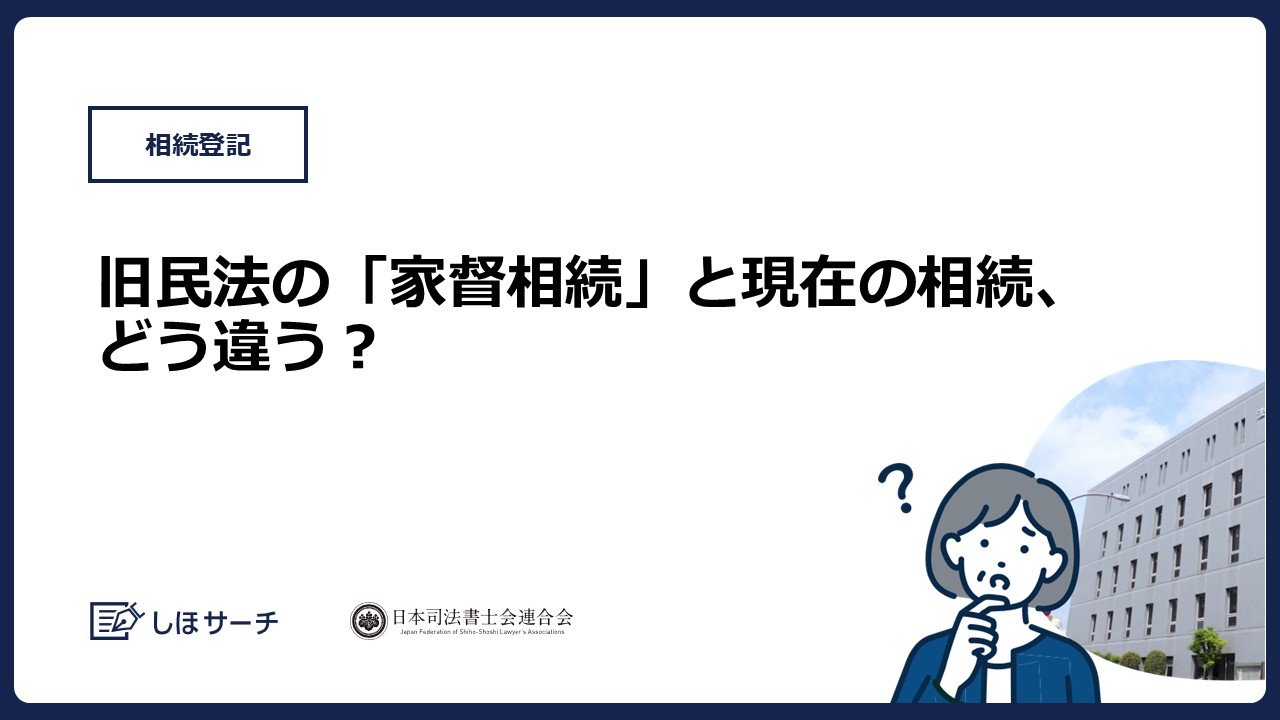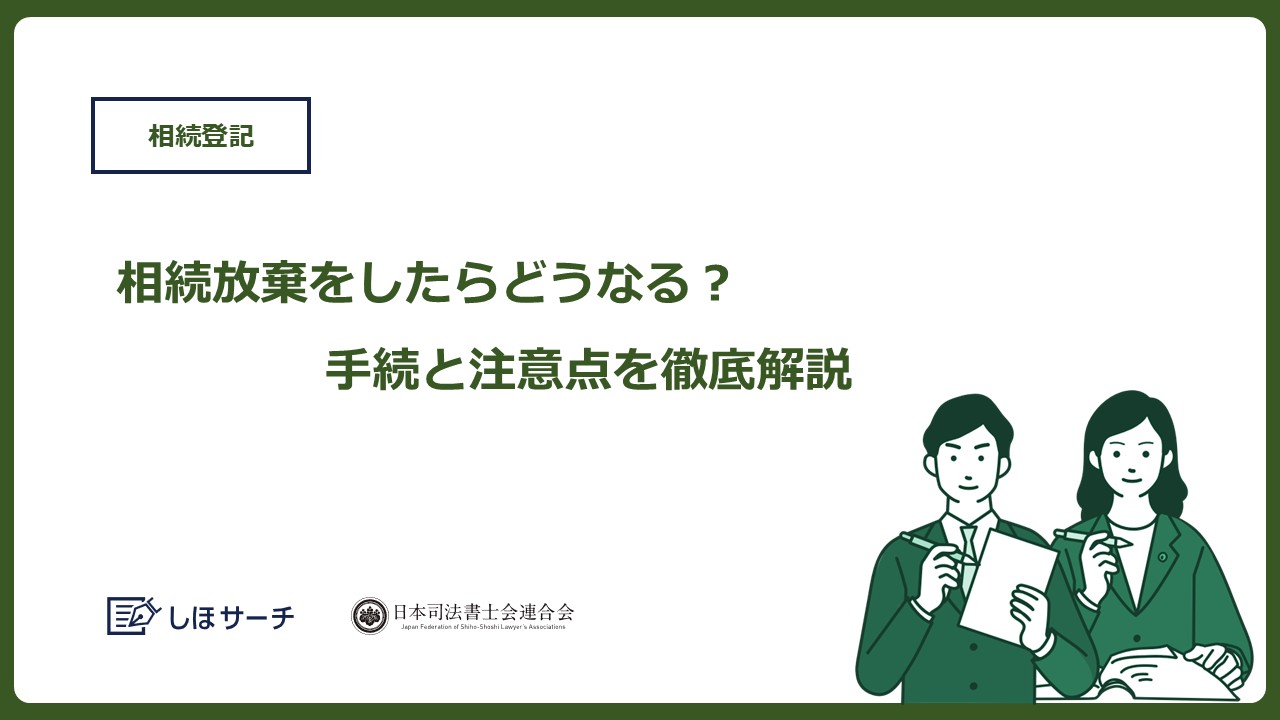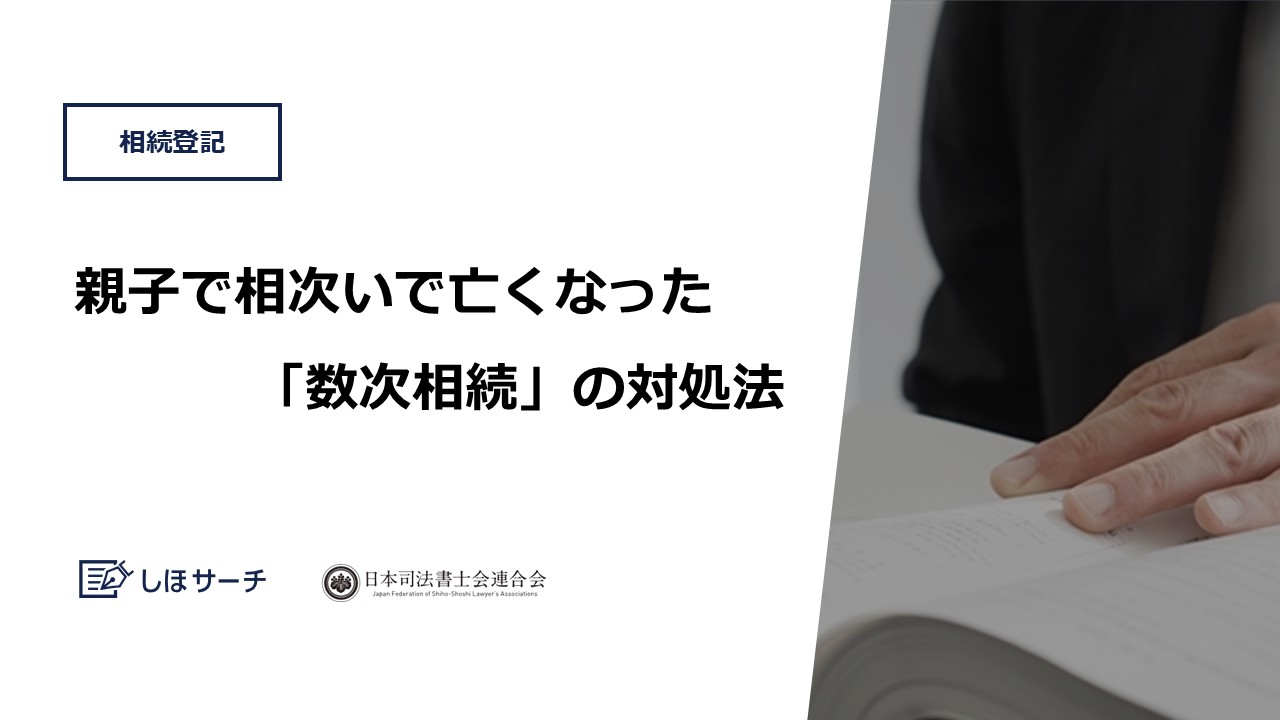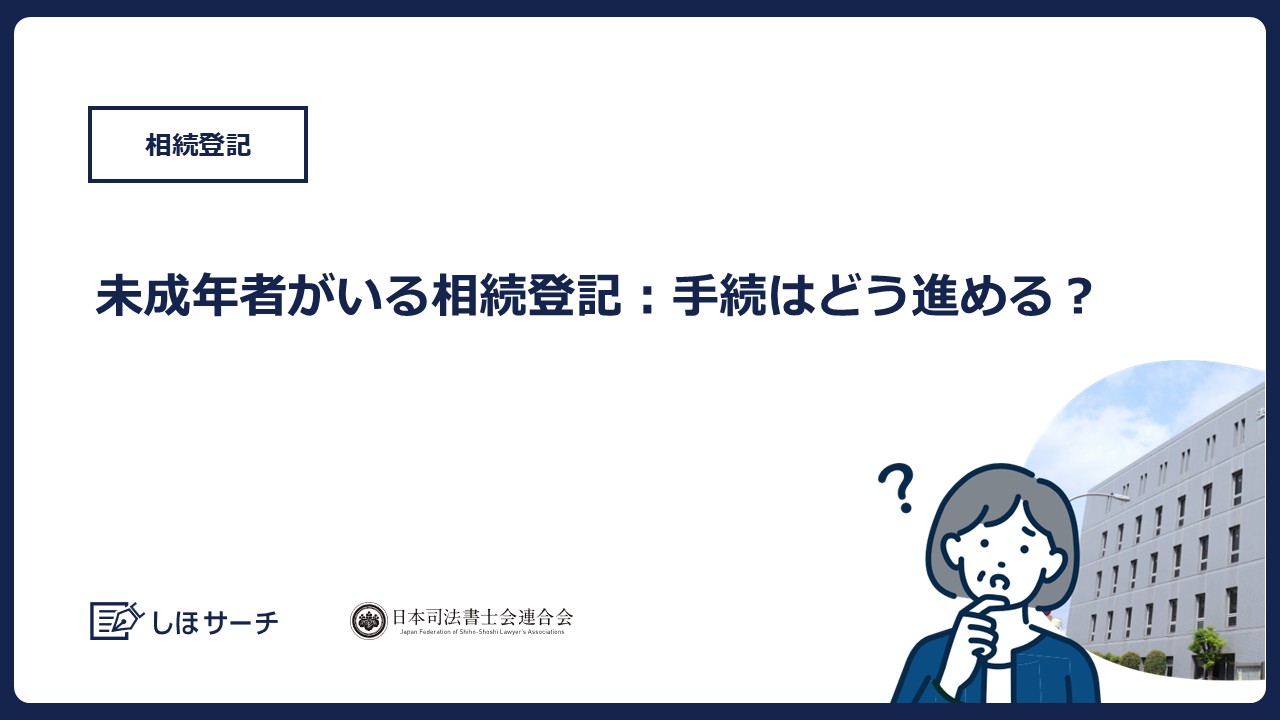「相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議」
遺産分割とは
遺産分割は被相続人の遺言による指定がある場合にはそれに従い(民法第908条第1項)、指定がない場合には、共同相続人は、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができるものとされています(民法第907条第1項)。そして、遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができるものとされています(民法第907条第2項)。
遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してすることとされており(民法第906条)、その効果は、相続開始の時に遡ってその効力を生じますが、これによって、第三者の権利を害することはできないものとされています(民法第906条)。
そして、遺産の分割は相続人全員によってする必要があり、遺産分割の前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができるものとされています(民法第906条の第2項)。
そこで、共同相続人の中に未成年者がいる場合には未成年者が単独で遺産分割協議に参加することができるかということが問題となりますが、未成年者が法律行為をする場合は親権者の代理(民法第818条)又は同意(民法第4条)を得ることが必要となり、未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときは未成年後見人が代理することとなります(民法第838条)。なお、児童福祉施設に入所中の未成年者に関しては、児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のない者に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行うこととされています(児童福祉法第47条第1項)。
未成年者とは
年齢18歳をもって、成年とする(民法第4条)こととされていますので、18歳に至らない者は未成年者として、法定代理人の同意を得ないでした行為については取り消すことができるものとして保護されます(民法第5条)。
令和4年3月31日以前は年齢20歳をもって、成年とすると規定されており、令和4年4月1日から上記のとおり成年の年齢が18歳に引き下げられました。成年年齢引下げにともない女性の婚姻適齢も18歳とされ未成年者に対する婚姻についての親権者の同意(旧民法第737条)や、未成年者の婚姻に対する成年擬制(民法第753条)については廃止されました。
未成年者を含む遺産分割における留意点
未成年者が遺産分割協議をする場合には以下の点に注意する必要があります。
(ア)利益相反
未成年者との遺産分割協議については、まず利益相反行為に該当するかどうかを注意しなければなりません。
共同相続人の中に親権者とその親権に服する未成年者がいる場合には、分割の協議をすることは利益相反行為(民法第826条)に該当するので、特別代理人の選任が必要となります。そして、未成年者が複数いる場合は、それぞれの未成年者のために異なる特別代理人の選任が必要となります(昭和28年4月25日民事甲第697号民事局長通達・昭和30年6月18日民事甲第1261号民事局長通達)。
(イ)未成年者の特別受益証明
親権者とその親権に服する数人の未成年者が共同相続人である場合に、未成年の子の全部又は一部について親権者が相続分のないことの証明書を作成することについては、特別受益は事実の証明であり、新たな法律行為をするものではないので、特別代理人の選任は要しないこととされています(昭和23年12月18日民事甲第95号民事局長回答) 。
なお、17歳の未成年者自らが作成した「相続分のないことの証明」は、当該未成年者の印鑑証明書の添付があれば、適正なものとして取り扱うこととされています(昭和10年9月21日民事甲第2821号民事局長電報回答)。これは未成年者であっても意思能力があれば特別受益証明書作成は事実の証明なので有効に行うことができるとするものです。
(ウ)未成年者の相続放棄
親権者と未成年の子が共同相続人の場合、親権者が子の相続放棄をするについては、相続放棄は単独行為であることを理由に判例及び先例は利益相反行為には該当しないこととされている民法第826条の適用がないとしています(昭和25年4月27日民甲1021号民事局長通達)。
しかし、昭和53年2月24日最高裁判所第2小法廷判決・民集32巻1号98頁は後見に関してではありますが、相続放棄が相手方のない単独行為であるということから直ちに民法第826条にいう利益相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でないとしながらも、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見人をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人自らが相続の放棄をした後にされたか、又はこれと同時にされたときは、民法第860条によって準用される同法第826条にいう利益相反行為にあたらないとしています。
当該判決理由中に以下の記述があるので注意が必要です。
共同相続人の一部の者が相続の放棄をすると、その相続に関しては、その者は初めから相続人とならなかつたものとみなされ、その結果として相続分の増加する相続人が生ずることになるのであつて、相続の放棄をする者とこれによつて相続分が増加する者とは利益が相反する関係にあることが明らかであり、また、民法八六〇条によつて準用される同法八二六条は、同法一〇八条とは異なり、適用の対象となる行為を相手方のある行為のみに限定する趣旨であるとは解されないから、相続の放棄が相手方のない単独行為であるということから直ちに民法八二六条にいう利益相反行為にあたる余地がないと解するのは相当でない。これに反する所論引用の大審院の判例(大審院明治四四年(オ)第五六号同年七月一〇日判決・民録一七輯四六八頁)は、変更されるべきである。しかしながら、共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者を後見している場合において、後見人が被後見人を代理してする相続の放棄は、必ずしも常に利益相反行為にあたるとはいえず、後見人がまずみずからの相続の放棄をしたのちに被後見人全員を代理してその相続の放棄をしたときはもとより、後見人みずからの相続の放棄と被後見人全員を代理してするその相続の放棄が同時にされたと認められるときもまた、その行為の客観的性質からみて、後見人と被後見人との間においても、被後見人相互間においても、利益相反行為になるとはいえないものと解するのが相当である。
以上のとおり、最高裁判決において原則として利益相反行為に該当するとされていますが(昭和60年3月22日東京高等裁判所判決・東高民時報36巻3号43頁も同旨)、登記実務においては形式的審査権しかない登記官として受理せざるを得ないのが現状と考えられています(登記研究400号190頁)。
司法書士の職責としては、登記官の形式的審査権を根拠として安易な未成年者の親権者による相続放棄手続による方法を選択すべきではなく、親権者が未成年者の相続放棄以前に相続放棄をしていない場合には特別代理人の選任手続を考慮すべきでしょう。
(エ)代襲相続の場合の未成年者の遺産分割
共同相続人の中で、代襲相続人が未成年者で、被代襲者の配偶者が存命の場合には、存命の配偶者は基本的に相続人ではないので、当該配偶者(親権者)が子を代理して遺産分割協議を行うことができます。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うことを要します(共同親権行使)が、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う(民法第818条第3項)こととされているので、被代襲者のために特別代理人や未成年後見人を選任する必要はありません。
未成年者が遺産分割協議をした場合の不動産登記の添付書類
遺産分割協議が整った場合は、当該遺産分割協議書を添付することにより遺産分割協議の内容を明らかとする必要があり、当該遺産分割協議書の真正担保として、遺産分割協議当事者の印鑑証明書(有効期限はありません)を添付することとなります。
なお、未成年者が、遺産分割協議の当事者である場合には、その親権者が法定代理人として遺産分割協議をし、遺産分割協議書にも親権者が実印押捺し、印鑑証明書を添付することとなります(前記代襲相続の場合の未成年者の場合等)が、通常は前述のとおり、未成年者と親権者の利益相反行為として特別代理人による遺産分割協議が行われますので、その場合には特別代理人の選任審判書の謄本及び特別代理人の遺産分割協議書への押印と当該印鑑に関する証明書が必要となります。
遺産分割の協議は成立したものの、相続人のうちの一人が遺産分割協議書への押印を拒んでいる場合は、この遺産分割協議により特定の不動産を単独で相続した者は、押印を拒んでいる者に対して、所有権確認訴訟の勝訴判決及び当該遺産分割協議書(他の相続人の印鑑証明書付き)を提供して相続登記の申請をすることができます(平成4年11月4日民三第6284号民事局第三課長回答)。
その他、通常の相続登記に関する添付書類である戸籍謄本等や住民票の写し等の記載より相続人であることを証明する必要があります。
しかし、遺産分割協議が整わなかった場合の遺産分割調停や、遺産分割審判による場合には、当該調停調書の謄本や遺産分割審判書の正本(確定証明書付き)が遺産分割協議を証する書面として添付書類となります。調停調書の場合は謄本でよく、確定証明書も不要です。
なお、相続人であることの確認は、遺産分割調停や遺産分割審判おいて、既に確認済みなので相続人であることを証する情報は必要ありません(昭和37年5月31日民事甲第1489号民事局長電報回答)。
胎児がいる場合の登記
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます(民法第886条第1項)が、生まれたものとすることに関して、停止条件説と解除条件説があります。この点、登記実務は解除条件説を採っていますので(明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答)、胎児名義の相続登記をすることはできます。その際には登記名義人となる胎児については住所・氏名がまだないので、どのように登記するかということが問題となります。
住所については母体である母親の住所を胎児の住所とすることができますが、氏名は「何某(母の氏名)胎児」とせざるを得ません。この表示方法に関しては、従前「亡何某妻何某胎児」とすべきとされていました(明治31年10月19日民刑第1406号民刑局長回答)が、夫婦でない場合もあり得るので、先例が変更されました(令和5年3月28日法務省民二第538号第2-2)。
なお、解除条件説を採っても、胎児自身が登記申請をすることはできませんので、未成年者の法定代理の規定が胎児にも類推適用して母親が登記申請することとされています(昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答)が、胎児を懐胎していることを証する書面は添付する必要はありません(登記研究191号72頁)。
ちなみに、胎児については母親が妊娠していることを知りながら胎児を無視して登記した場合、当該登記は一部有効であるので、無効とまでは言えませんが、胎児が出生した場合には、胎児を登記名義人とする更正登記をする必要があります(胎児が死産だった場合には何ら登記する必要はありません)。
また、胎児の登記ができるとしても、母親が胎児を代理して遺産分割協議をすることはできません (昭和29年6月15日民事甲第1188号民事局長回答) ので、胎児を無視した遺産分割協議の結果で登記した後に、胎児が出生した場合については、法定相続分での登記への更正登記をする必要がありますが、胎児の出生後特別代理人を通じて遺産分割協議をした場合については遺産分割協議の遡及効により、当該遺産分割協議の結果の登記への更正登記をすることができるでしょう。
その際の登記手続については、遺産分割協議の日をもって登記原因を遺産分割として登記権利者が単独申請で更正登記をすることができます(令和5年3月28日法務省民二第538号第3-1)。