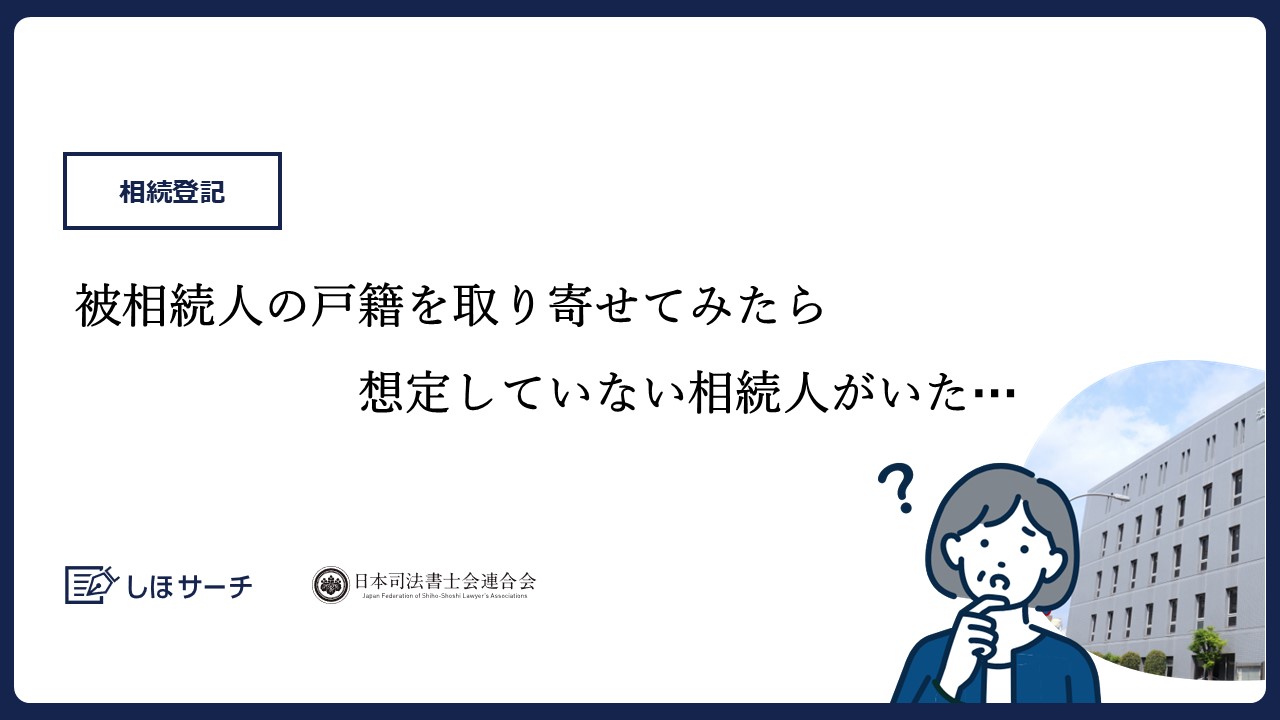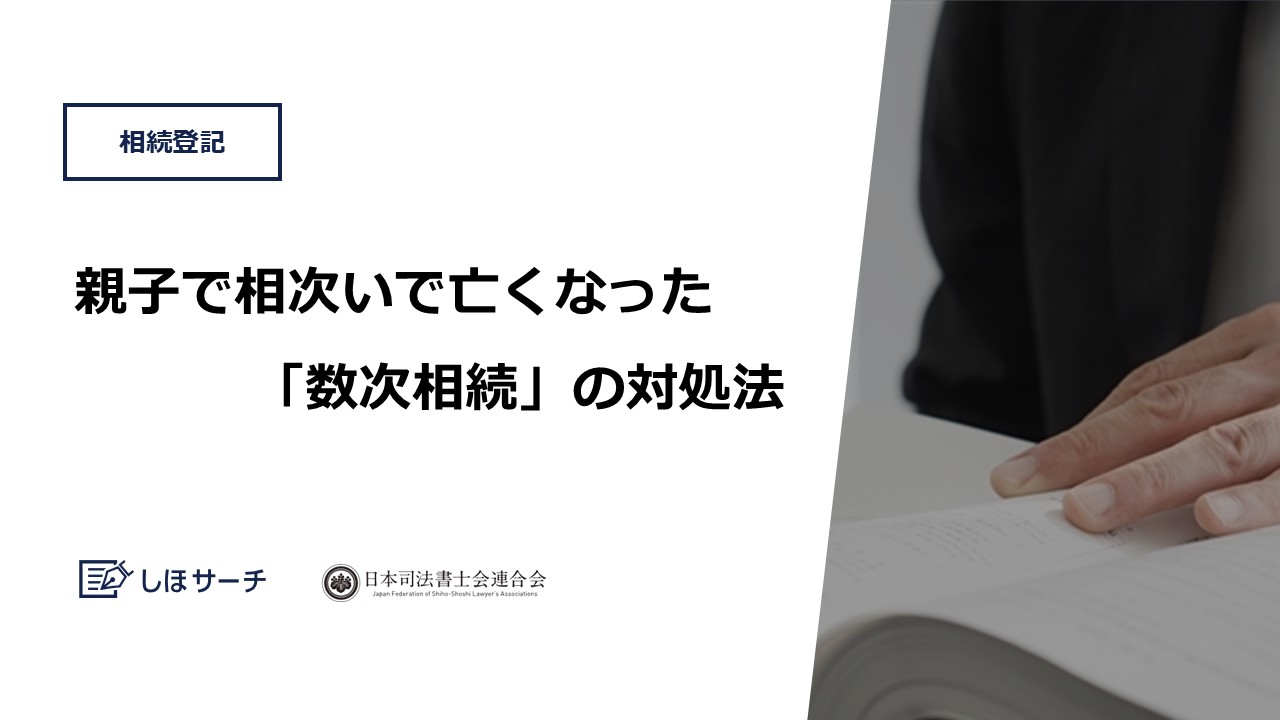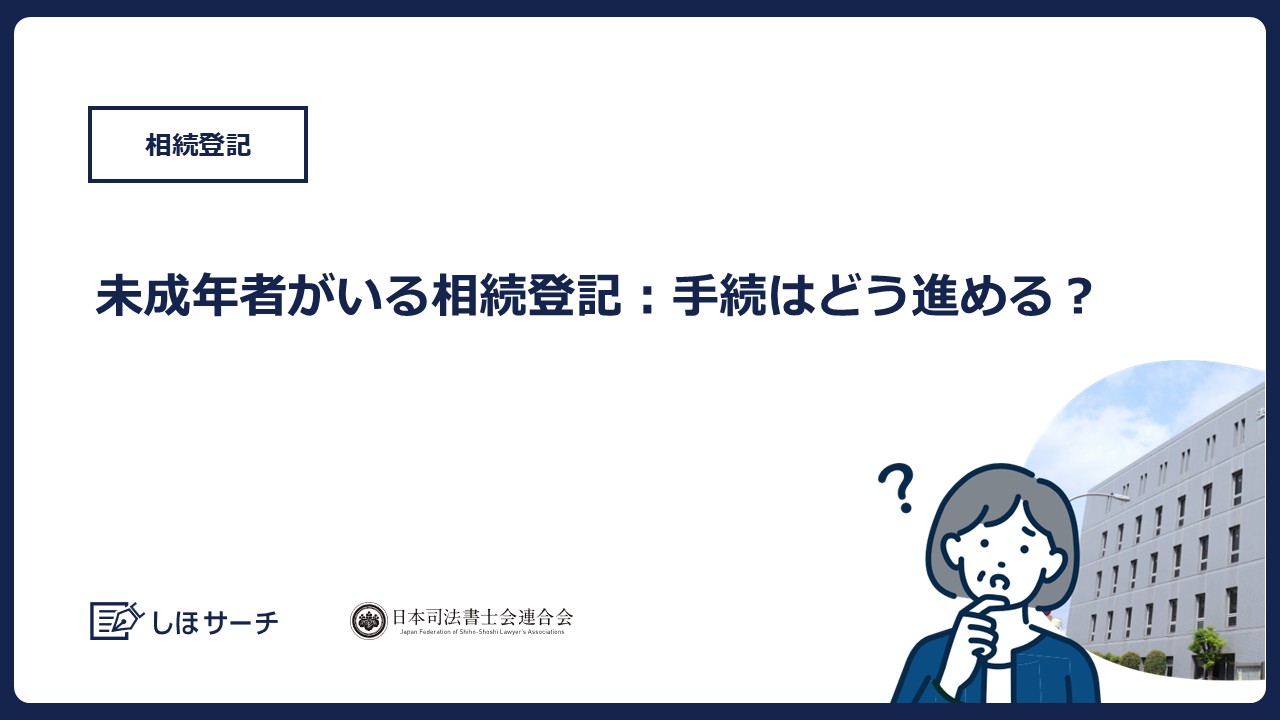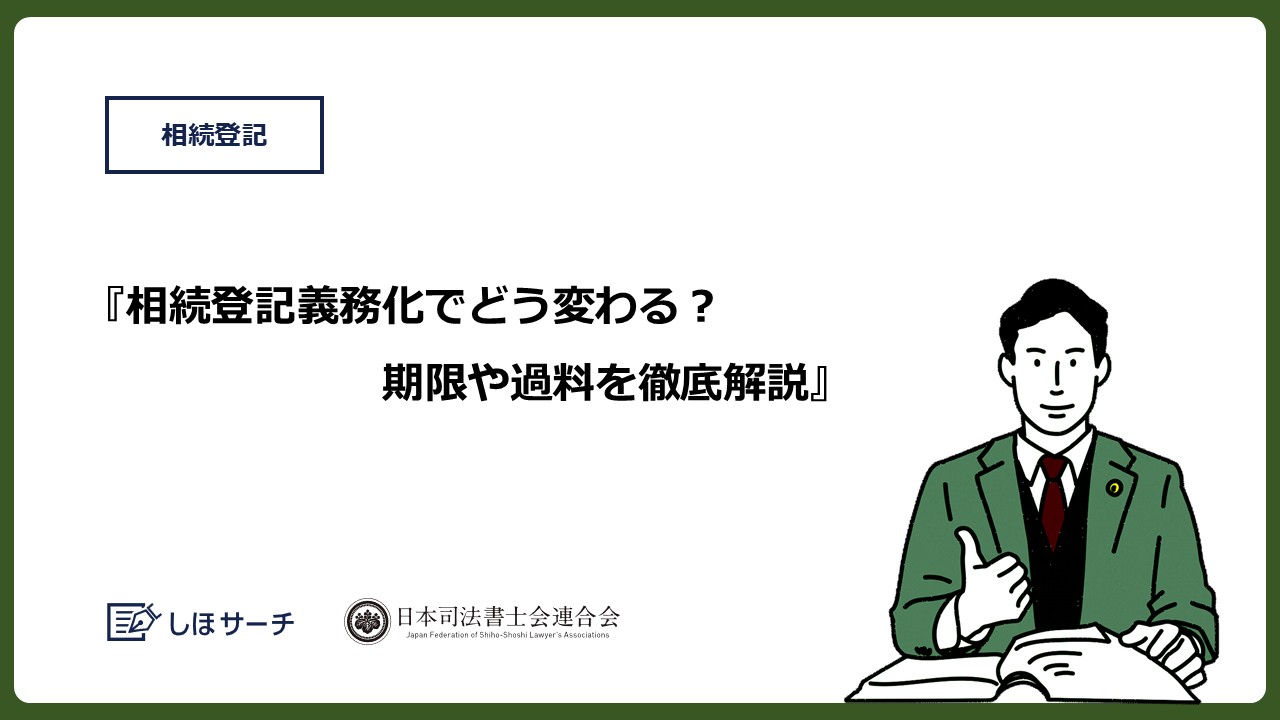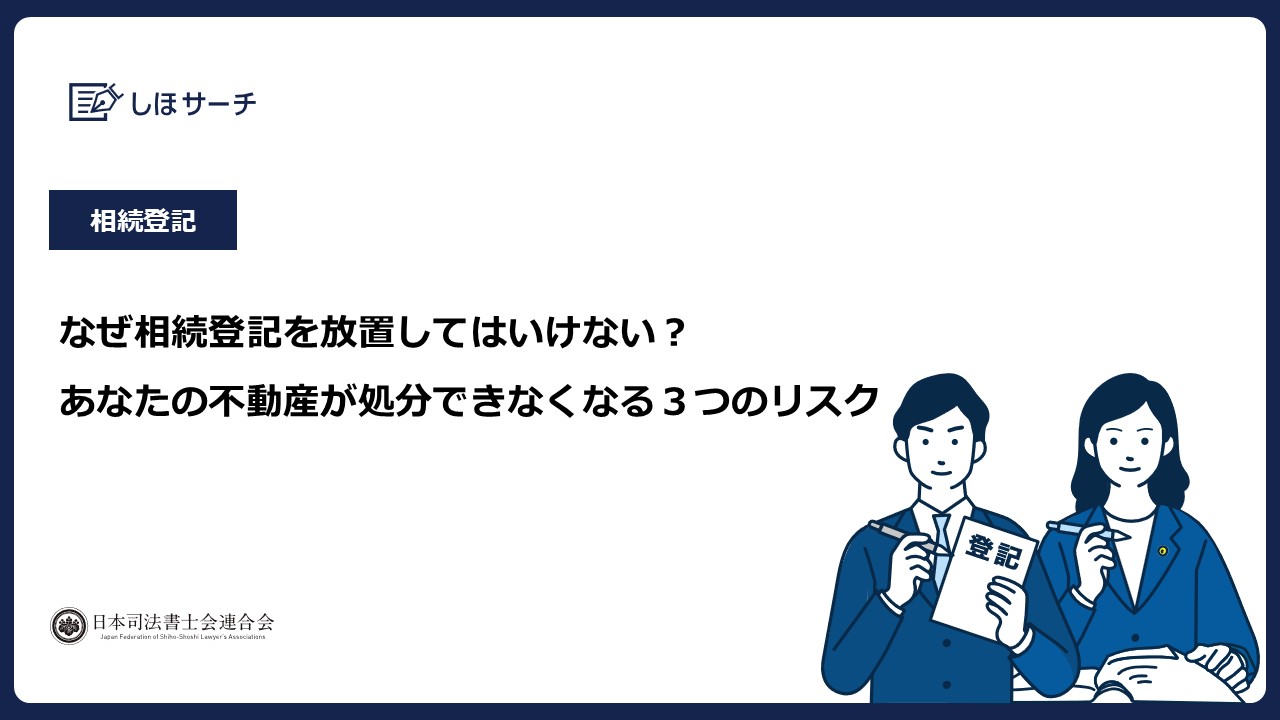被相続人の戸籍を取り寄せてみたら想定していない相続人がいた…
相続人の確定
相続が発生し、相続に関する手続をする際、最初に行うことは、「誰が相続人なのかを確定する」ということになります。被相続人の遺産を誰に相続させるかを相続人間で協議するためには、「誰が相続人なのか」を確定させておかないといけないためです。相続人の確定につきましては、しほサーチコラム『誰が相続人になりますか』を参考にしていただけましたら幸いです。
(リンク)https://souzoku.shiho-shoshi.or.jp/column/004/
想定していない相続人の発覚
被相続人の戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍について、被相続人の出生から死亡まですべて取り寄せることにより、誰が相続人なのかが確定することになります。そこで発覚するのが想定していない相続人の存在です。相続手続を進めていく中で大変になるケースが、被相続人の前配偶者(前夫・前妻)との間に子どもがいたケースです。このケースの場合、家庭裁判所に相続放棄の手続をしたなどの事情がないかぎり、原則としてその前配偶者との間の子どもについても相続人になります。生前、被相続人から前配偶者との間の子どもの存在が伝わっていれば心の準備もできているかもしれませんが、そうでない場合は青天の霹靂ということになってしまいます。このような想定していない相続人が発覚した場合はどのように遺産分割協議や相続手続を進めていけばよいのでしょうか。
丁寧なやり取り
本ケースのような場合、その子どもと元々面識があるのかそうでないのかによって対応は変わってきますが、いずれにしても丁寧なやり取りを心掛けることになるでしょう。どのような遺産分割協議になるとしても「私が土地と家屋を相続するつもりだから」と一方的な内容の遺産分割協議書を作成して送りつける行為はトラブルの元になってしまいます。まずは、被相続人の死亡の事実や、相続人である旨を丁寧に手紙などの文書でお伝えすることからはじめるのがよいのではないでしょうか。ご自身が「逆の立場だったらどう伝われば納得するだろうか」と仮定して慎重に進めるのがトラブル回避の第一歩となります。ボタンの掛け違いが後々相続人間の大きな遺恨となるケースは枚挙にいとまがありません。
もっとも、丁寧な対応をしたとしても、遺産分割協議が整わないケースはあります。その場合はどうしたらよいのでしょうか。
遺産分割調停の申立て
相続人当事者間での遺産分割協議が整わなかった場合、当事者同士で話を進めることは困難になってしまいますから、裁判所の力を借りることが考えられます。遺産分割協議の場合、まずは調停の手続を利用することになります。遺産分割調停の申立ては、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人を相手方として申立てをします。申立先は相手方のうちの1人の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。申立てに必要な費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円です。遺産分割調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、相続人それぞれの主張を聞いていき、最終的に相続人全員による合意を目指していきます。
それでも、合意がまとまらない場合は調停不成立ということで審判手続が開始されることになります。審判手続は、裁判官が遺産に属する物または権利の種類および性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。当事者同士で協議を進めることは仕事や私生活に与える影響も大きいです。調停申立書をはじめとした裁判所に提出する書類の作成を司法書士に依頼することも可能ですし、相手方と交渉を要するケースでは弁護士に依頼することも視野に入れてください。
まとめ
相続の手続を進めていく中で、想定外のことはどうしても起きてしまいます。本ケースのような事例は少なくありません。お互い血のつながった血縁同士の話とはいえ、遺産が絡むとどうしても話し合いがスムーズにいかなくなることは多々あります。被相続人と前配偶者との当時の関係性も影響を大きくします。また、遺産分割協議には相続人だけではなく、相続人の配偶者や親族などの影響があることも否定できません。各相続人の関係者の思惑が相互にぶつかり合うため、揉めてしまうケースがあることは皆様ご承知のとおりです。
想定外のケースが起きてしまったときはまずは焦らず最寄りの司法書士にご相談ください。適正な手続をご案内することはもとより、感情に寄り添った対応を心掛けて、依頼者と二人三脚で進めてまいります。